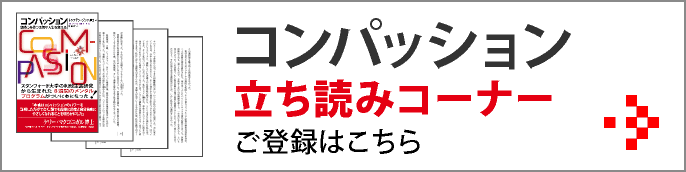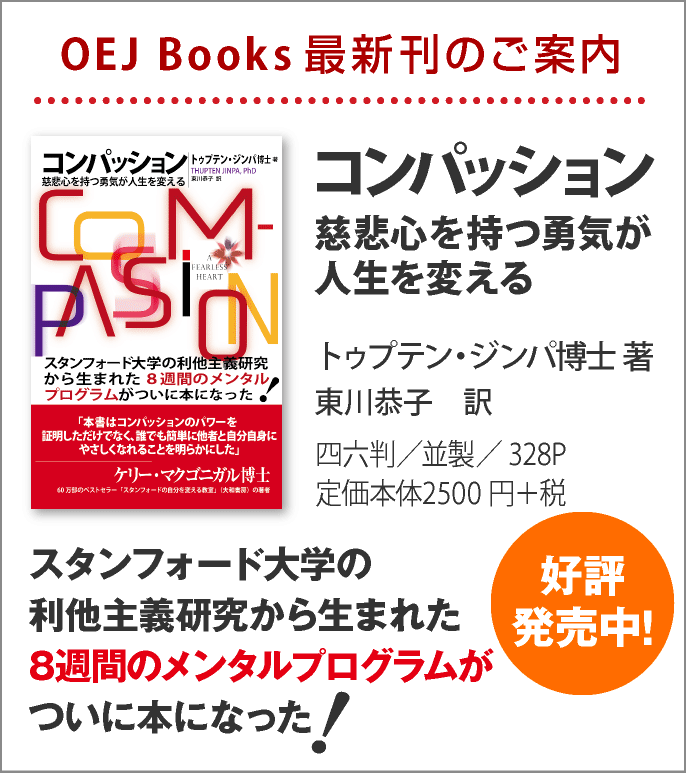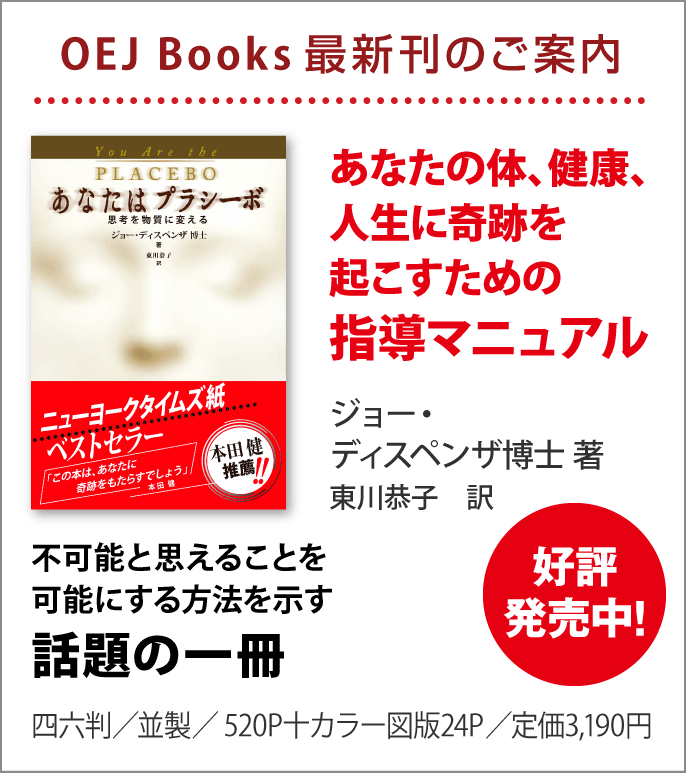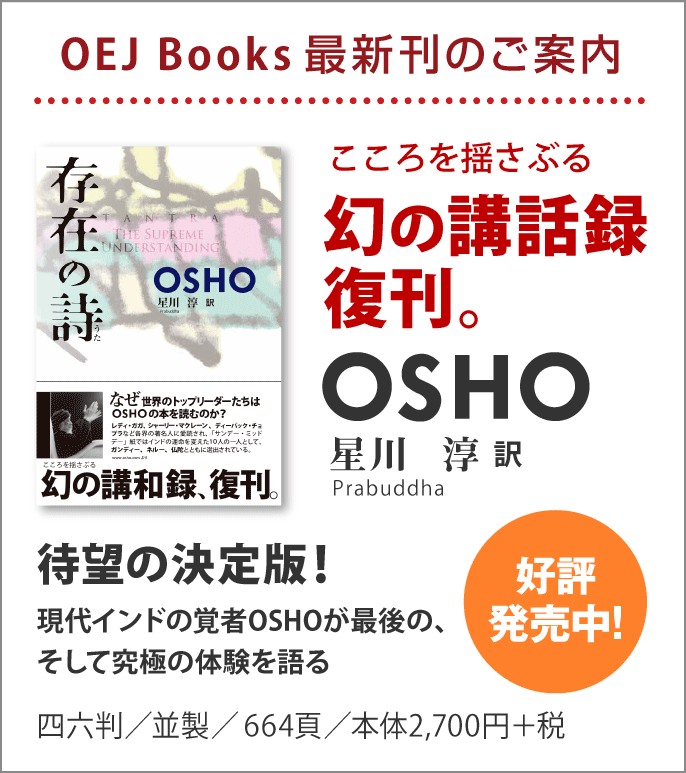OSHOが最後にブッダフィールドに現れてたのは1月16日で、肉体を離れたのは、その3日後の1月19日でした。OSHOは、悟りを得た人が肉体を離れたときに起こる、さまざまな現象についても語ったことがありました。その悟りの意識が肉体から解き放たれるとき、その近くにいた人たちにも、その意識が経験されうるというのです。シュンニョが体験したような、「自分が柔らかな至福に包まれるのを感じました。『これが私にひそんでいるもの、私に起こりうるもの、私の可能性なんだわ』ということも、そのようなことのひとつでしょう。
そしてまた、シュンニョは自分の意識を選択できるということにも気づきます。
「自分がそれを選択しさえすれば、私はこのようにして生きられるのです」
「闇に落ちていきたいという誘惑、絶望したいという誘惑を感じる一方で、自分には選択する力もあること、闇にとどまらないことを選択する力もあることを感じていました。そこに選択肢があることは明瞭でした」
シュンニョは書いています。
「OSHOが死ぬ前の最後の二晩、私はブッダホールでの瞑想に最後までいられませんでした。講話のビデオが流れている途中に席から立ち上がり、ブッダホールから駆けだして、私の洗濯部屋、私の子宮に向かったのです。
私たちは彼がいないままブッダホールに座って瞑想しました。
インド音楽の演奏と沈黙。
OSHOはインド音楽が好きでした。
西洋音楽よりも瞑想的だと言っていました。
その次の日、私はリキシャに乗っていて、自分が柔らかな至福に包まれるのを感じました。
「これが私にひそんでいるもの、私に起こりうるもの、私の可能性なんだわ」と、私は自分に言いました。
自分がそれを選択しさえすれば、私はこのようにして生きられるのです。
その日は、それから一日中、私は自分がどんなふうに気を動転させるのかを観ていました。どうして自分がそうなのかはわからないまま、私は自分の現実の姿、マインドにとらわれやすい自分の癖をはっきり見たのです。闇に落ちていきたいという誘惑、絶望したいという誘惑を感じる一方で、自分には選択する力もあること、闇にとどまらないことを選択する力もあることを感じていました。そこに選択肢があることは明瞭でした。ずっと、こうしたことを感じながら一日が過ぎました。
私は自分の部屋で座りました。
私の部屋はOSHOの部屋の真上でした。
私は文字どおりOSHOの天丼に住んでいたのです。
とても冷え冷えとした天丼でした。
その日の午後、私は自分の書いていたおとぎ話の最終章を書いてすごしました。
そのおとぎ話は、この本のエピローグになっています。
午後6時になる寸前、その最終章をプリンターから打ち出すために、アナンドのオフィスに座っていると、マニーシャが泣きながら入ってきました。
「OSHOは死ぬところだと思うわ」と彼女は言いました。
私たちはふたりとも、インド人の医者が家から出て行くところを見ていました。よほど容体が悪くなければ、OSHOが外部の医者から往診を受けることはありません。
ですから、とても深刻なことが起こっているはずです。自分の部屋に戻り、7時の瞑想に行く用意をしていると、私の禅の友であり、恋人でもあるマルコが来ました。夜の瞑想に向かう前、ふだんなら私たちは、いっしょに踊ったり笑ったりするのでした。でも、その晩の私たちは、起こりつつある恐ろしいことのために凍りついてしまった亡霊のように、ただ立ちつくしていました。
マルコは白いローブをまとい、1月からショールをかけていました。
「君の眼にある動揺を見るとぎょっとしてしまう。なにが起こってるの?」
まだはっきりとは知らないけれど、OSHOになにかが起こっていると思うと私は答えました。
マニーンャが部屋に来て、OSHOは肉体を離れたと言いました。
彼女は泣きだし「腹がたつわ。彼らが勝ったのね」と言いました。「彼ら」というのはアメリカ政府のことです。私は言いました。
「そんなことないわ。今にわかる。彼らにはOSHOを殺せないわ」彼女が行ってから私がした最初のことは、ベッドに身を投げ出して、OSHOに向かって呼びかけることでした。
『OSHO、まだはじまったばかりです。私はこれがはじまりだと知っています」その瞬間は意識がはっきりしていたのですが、やがでショック状態に入ってきました。眼は一点を凝視したまま、とてもゆっくりと階段を昇ったり降りたりしました。どこへ行こうとしているのか、なにをしようとしているのか、自分でもわかりません。そのころになると、みんなにも知らせが届き、アシュラム中から泣き声が聞こえてきました。私はムクタに会いました。
彼女はOSHOを焼き場に運んでいく担架に載せるバラを、OSHOのバラ園から摘んでいました。私はバラを乗せるための、なにか美しいものがないか探しました。
なにかをしている方が気が楽でした。
直径が120センチほどの銀の盆が見つかりました。
パルシー教(拝火教)の 結婚式で使われるものです。
ザソーンから贈られたもので、和尚はとても気に入っていました。何年も前からOSHOの運転手をしていたアヴェッシュが玄関先に立っていました。今夜はOSHOをブ ッダホールに乗せていくのかどうか知りたがっています。
彼はおびえた顔をして「なにが起きているのかわからない」と言いました。
彼は誰からも聞いていなかったのでした。
私は彼を引き寄せて、腕に抱きしめましたが、言うべきことが口にできません。
しばらくしてから、私は彼に「私には言えない」と言いました。
アヴェッシュは私をじっと見つめ 「彼は行ったのか?」と言いました。
それから彼は泣き崩れましたが、私はそばにはいられませんでした。
その晩の私たちは、各人がそれぞれのひとり在ることのなかに深く入っていったようでした。
すべてのサニヤシンは、一人ひとりがOSHOとのあいだに独自の親密な関係を結んでいます。
他人が足を踏み入れることはけっしてできない関係です。
廊下でアナンドに会いました。
彼女は光を放っていました。
アナンドは、私をOSHOの部屋へ連れて行きました。
OSHOはベッドに横たわっています。
彼女が私を残して部屋を去ったあと、私は床の上にひれ伏し、冷たい大理石に額をつけて、つぶやきました。
「私のマスター」
感じられるのは感謝だけでした。私はOSHOをブッダホールに運ぶのを手伝いました。バラの花でいっぱいになった彼の担架をポディウムに置きました。彼はお気に入りのローブを着て、日本の女性見者から贈られた、いくつもの真珠を散りばめた帽子をかぶっています。
そして、一万人のブッダがお祝いしました』
「和尚と過ごしたダイアモンドの日々」
(本書は絶版になっています。 お問い合わせはinfo@oejbooks.comまで)