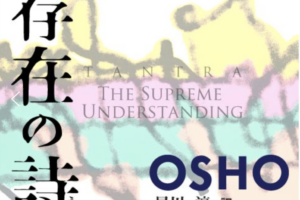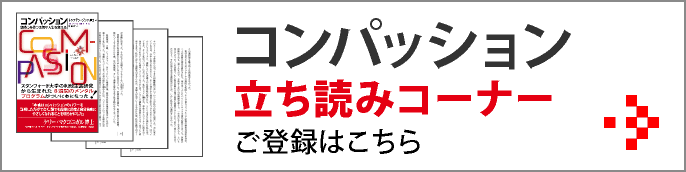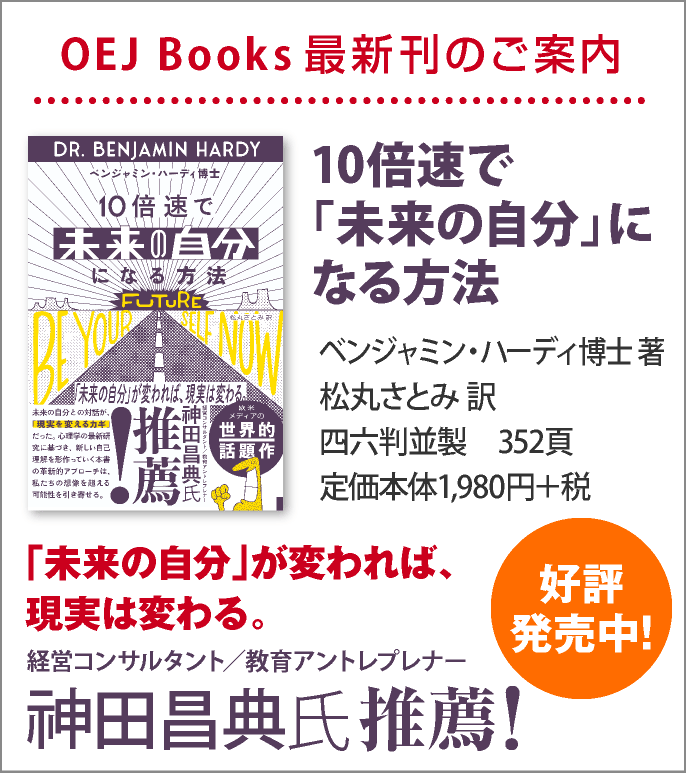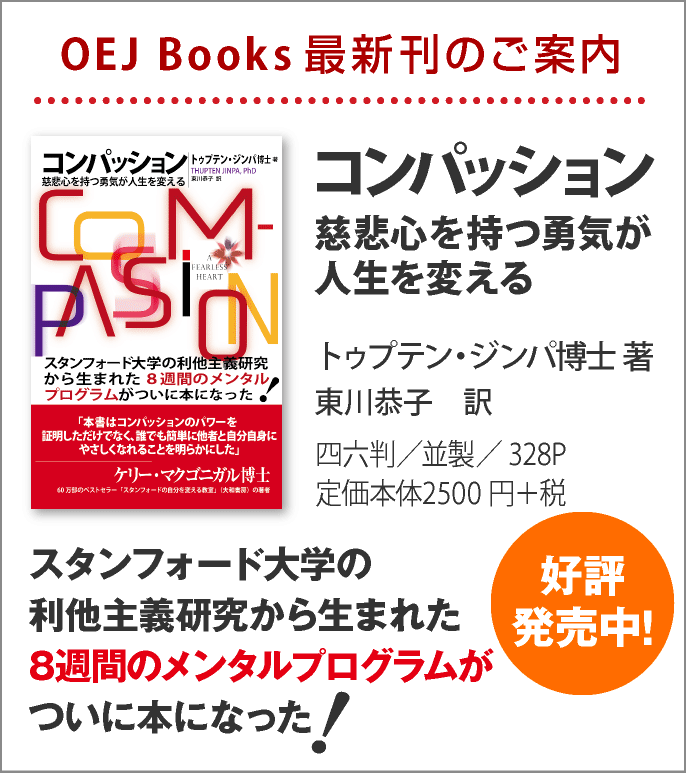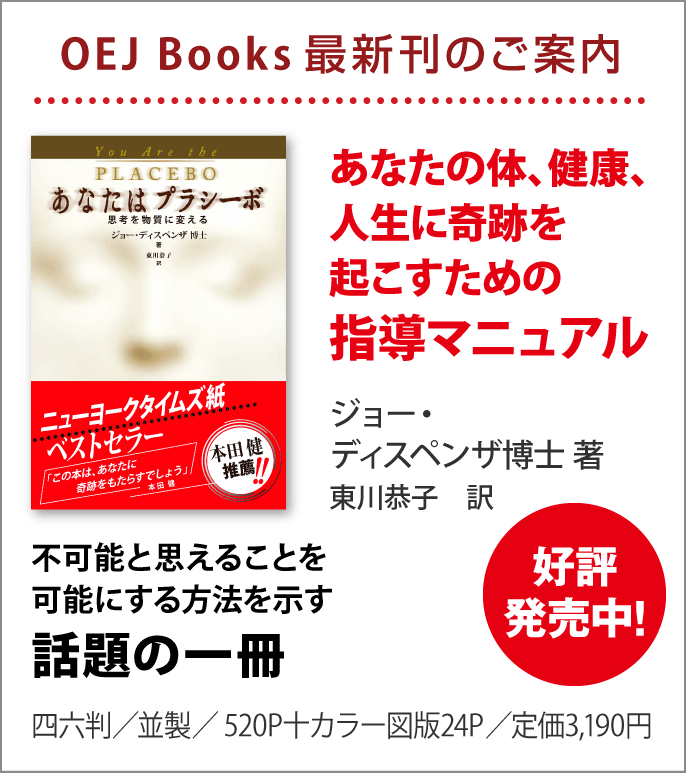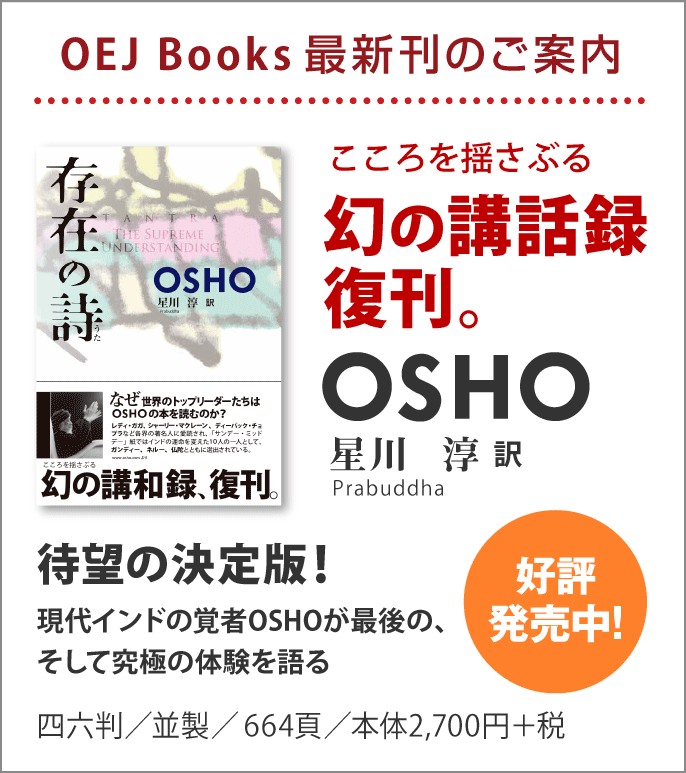いよいよこのシュンニョの本での関係性の探求についてのシリーズのお話は、終わりを迎えます。
シュンニョにとっては「男と女の関係のすべての次元を可能なかぎり探究し、あらゆる激情と無意識の欲望を生き抜くことが必要だった」のです。
そして、そのシュンニョの男と女の関係の探求は、Oshoの洞察によって、どのようになっていったのかということがよくわかります。
それはシュンニョにとってはそうであっても、誰にもそれが当てはまるとはかぎらないし、人それぞれの男と女の関係の探求があるでしょう。
この本に書かれてあるシュンニョのお話は、Oshoの言葉や洞察が単に言葉ではなく、それはひとつの実験の機会になるということの例にはなると思います。
Oshoは常に「私の言葉を信じないように」と語っているのを耳にします。
自分で試してみてみなさい、と。
そうすれば信じる必要はなく、自分の理解になるだろうと。
Oshoが語っていることは自分にはあわないことかもしれないし、自分に向けての言葉ではないかもしれません。
それがほんとうかどうかは自分で試してみて、それを生きてみることでしか、それが本当に自分に役に立つものであるかはわかりません。
Oshoはあらゆることについて、あらゆる角度から、あらゆる人に対して語っているので、その言葉が自分に当てはまるものなのかどうかは、自分で試してみる必要があったりもします。
もっとも、十分な理解があれば、いちいち試行錯誤をしなくてもすむものですが、はじめのうちは試行錯誤するうちにその理解が育ってきたりもします。
今回のシュンニョの関係性についてのお話は、そういうシュンニョの試行錯誤の物語として、自分が探求を深めるうえでの参考になるものです。
本というのは、そういう自分ではできない体験を自分の代わりにしてくれているようなものなので、シュンニョの体験から、男と女の関係のさまざまな次元を理解する機会にもなったのではないかと思います。
シュンニョは最近になって、やっと
「嫉妬があるところには愛はない、
嫉妬はセックスに関係しているが、
愛とは無縁だ」
というOshoの言葉を理解するようになりました、と書いています。
とはいえ、Oshoがシュンニョに男女の関係について語った最後の言葉はこうでした。
あらゆる恋愛は災難だ
これはさまざまな恋愛問題について質問を受けてきたOshoの洞察なのでしょう。
恋愛を災難にしてしまっているのが私たちの現状ということでしょうか。
シュンニョは語っています。
「私が思うには、スピリチュアルな道は、高い山のいただきへと至るらせん状の道のようです。
そのため、私は何度も同じような幻想(トリップ)にはまったり、同じような感情にとらわれたりするのですが、それは毎回、少しずつ違ったものになっています。
少しずつ高く登り、少しずつ意識的になっているのです。
サニヤシンになる前の私は、ひとりの男性と深く関わるのをやめることで、自分が嫉妬を感じるような状況を避けてきました。
ローレンスだけが例外でした。
彼は私が安心できるようなやりかたで愛してくれました。
私たちは一緒に暮らしていましたが、それでも彼は、ほかの女たちとも親しくしていました。
彼がなかでも大好きで、ひんぱんに会っていた女性がいました。
ローレンスは彼女を家に連れてきて、私に会わせました。
私の友人たちはこう言ったものです―――
「あなたは彼を愛していないのね。だって嫉妬してないじゃない」
私もそう言われて不思議に思いました!
私は最近になってやっと
「嫉妬があるところには愛はない、
嫉妬はセックスに関係しているが、
愛とは無縁だ」
というOshoの言葉を理解するようになりました。
私には、男と女の関係のすべての次元を可能なかぎり探究し、あらゆる激情と無意識の欲望を生き抜くことが必要だったのです。
道の途上にある、すべての探究者が同じことをしなければならないとはいえないかもしれません。
それは私にはわかりません。
私は何年もかけて、自分のなかにいるドラゴンや悪魔が力を得て、その醜い頭をもたげるのを見てきました。
ですが、いったんそれが自覚されると、私は意識的に努力して、そうしたものを、私の自由を妨害する習慣的なパターンとして見られるようになるのです。
私のなかには女性特有の要求する態度があります。
以前にくらべて、ずっとはっきりとそれが観られるようになりました。
それは驚くような依存です。
ですがそれに気づくことにより、私とそれのあいだには距離が生まれ、それに自分が染まりきることはなくなります。それはただ、訪れては去るのです。
たとえば恋人に「さよなら」と言うと、彼は「またね」と言うかもしれません。
私は彼に言葉を返さずそのまま笑顔を浮かべていて、一見すべては問題ないようなのですが、それでも私は自分の目がうつろになり、まるで乞食のようになにかを要求しているのに気づきます。
内側ではこんな声がしています。
「またね」ですって? いつまた会ってくれるの? どこで? いつ? 何時に?
ですが私はそれに気づいています。
一瞬ですが「どこで? いつ? また会えるの?」と言っている自分に気づいたのです。
そこには、たしかに要求がありました。
そして、それを認めたとき、私はそれが原始時代にまでさかのぼる女性特有の態度であることに気づきます。
そのころの女たちは完全に男に頼っていたのでしょう。
洞窟で暮らす女や子供たちは、男が持ち帰る穫物の肉に頼りきっていたはずです。
ですがそれはむかしの話です―――
いまの私は肉を食べることさえしません。
軽く遊びに満ちたやり方で、ほかの人と一緒にいること。
ふたりのあいだの親愛関係を日々の交感としてのみとらえること。
おそらくOshoは、私たちをそうした方向に導こうとしてきたのでしょう。
もっとも、男女の関係についてOshoが私に語った最後の言葉はこうです―――
あらゆる恋愛は災難だ」
「OSHOと過ごしたダイヤモンドの日々」
(本書は絶版になっています。 お問い合わせはinfo@oejbooks.comまで)