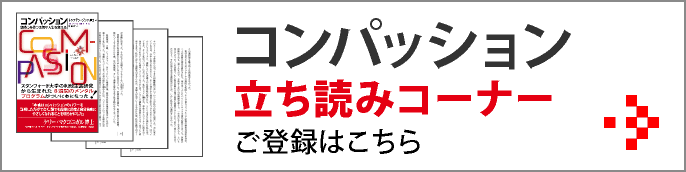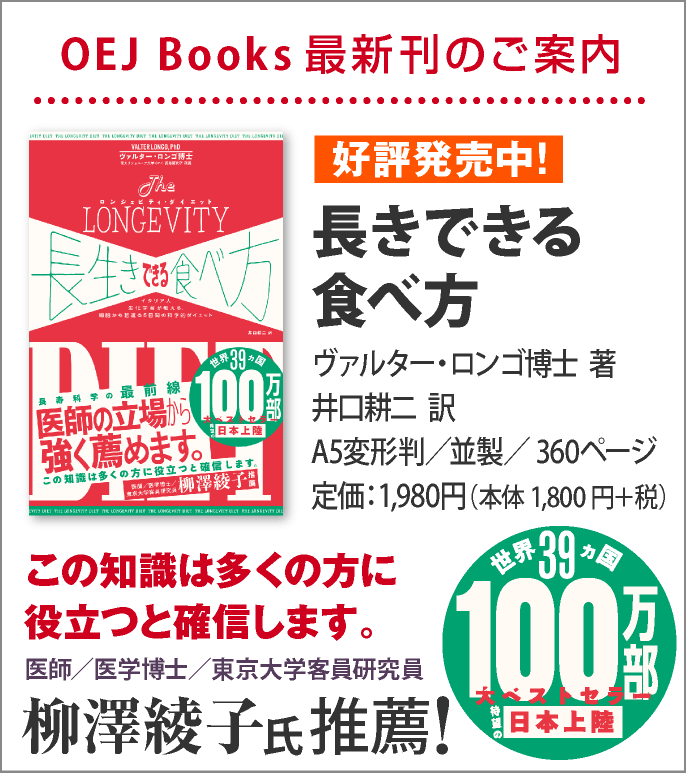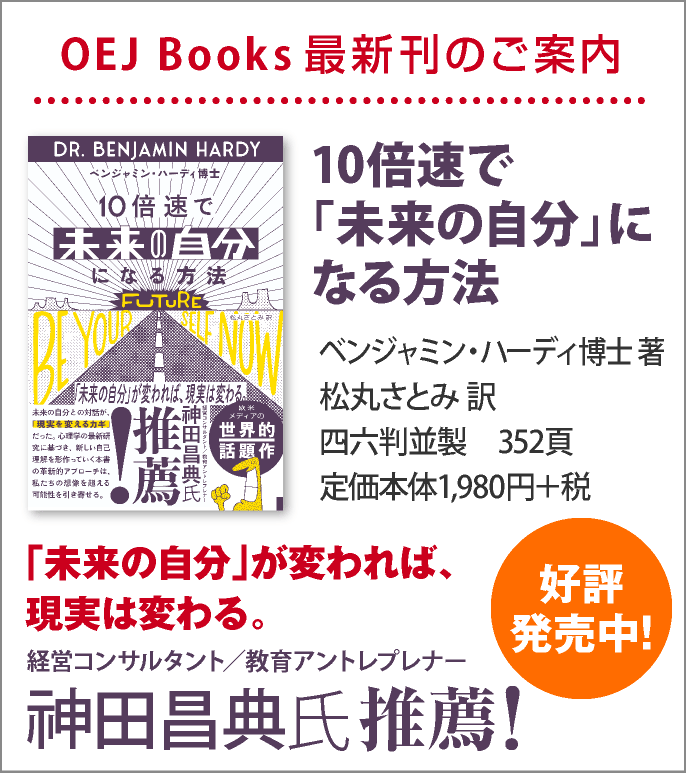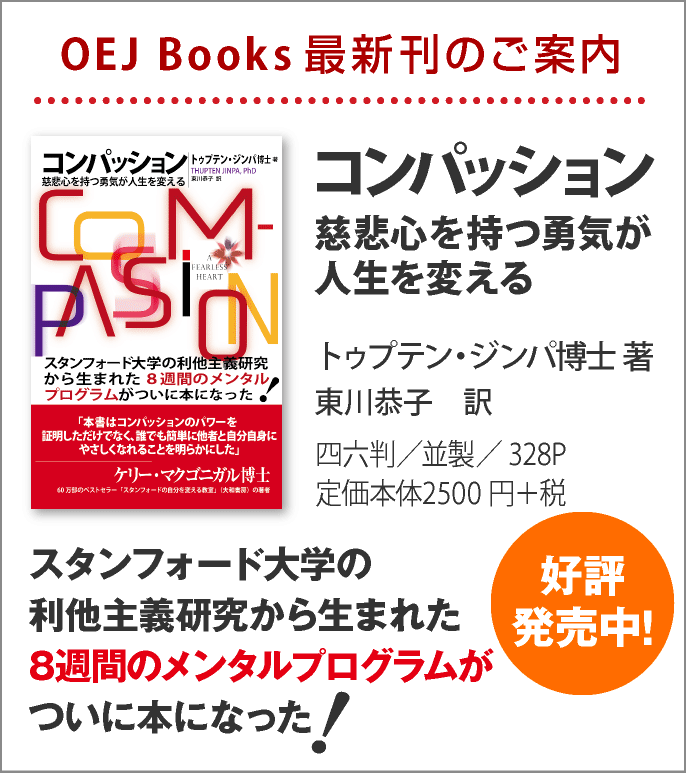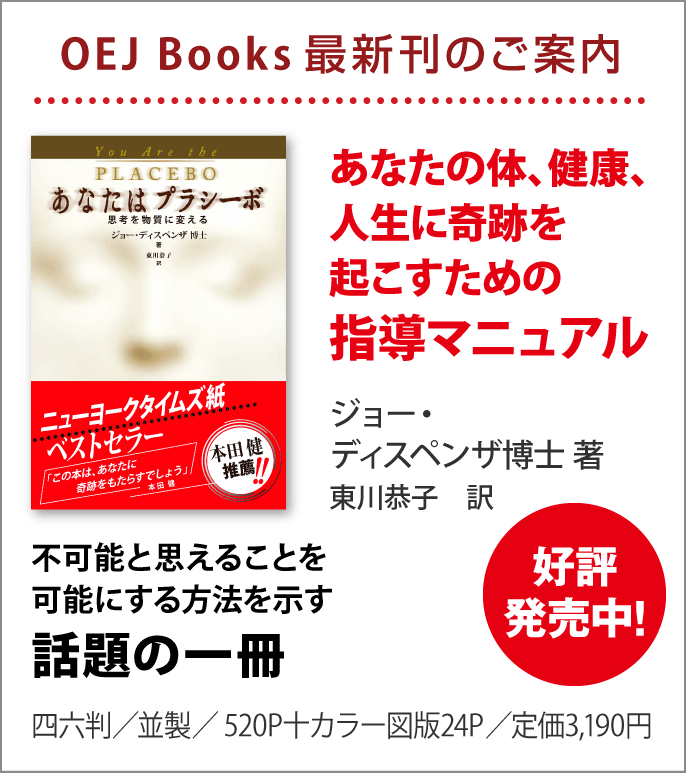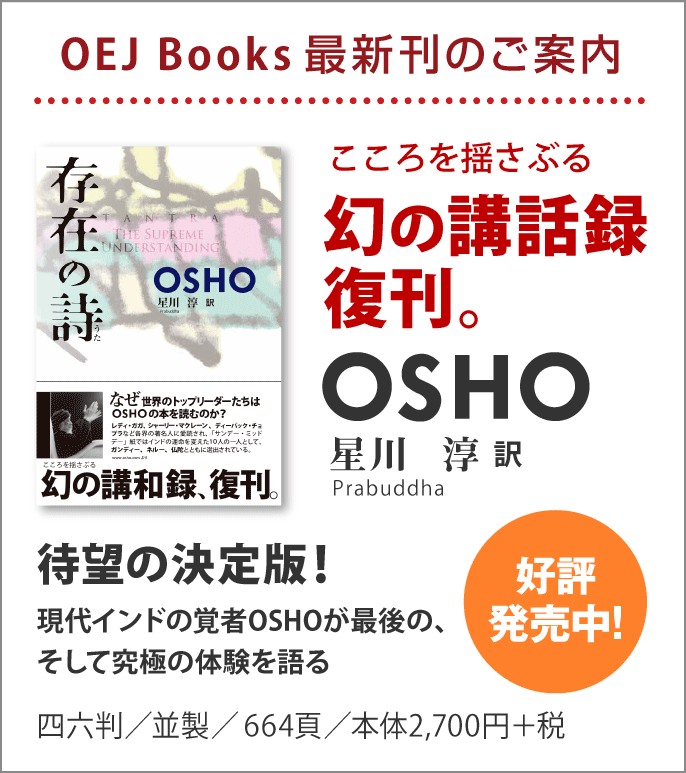幽霊はいるのかいないのか?
幽霊といえば、通常死者の幽霊ですが、生きた人間でも幽体離脱して幽霊になることもあります。
科学的に考えれば、エントロピーの法則があるので、煙が拡散するように幽霊のような実体は存在しえないという説があります。
またOSHOの言うように、恐怖が作りだした産物でしかない、とも言えるでしょう。
かと思えば、そういう幽霊の実体を見たり、経験したという体験談にもことかきません。
OSHOがシュンニョをからかってのことなのかどうかはわかりませんが、OSHOが幽霊を見たという話があったりもします。
私の感じでは、そういうものが存在しうる次元というのは、なんらかの形であるような気はしています。
学生時代のある時期、金縛りにしばしばあっていたことがあったのですが、その時期に、このようなことがありました。
ある暑い夏の日、4畳半の学生長屋の部屋を開けっ放して昼寝をしていると、廊下を誰かが歩いて私の部屋に入って来たので、起きようとすると金縛りで身動きできず、その人は私の寝ている横に座ったのす。
そちらを向こうとしても首がまわらず、自分の目は開いているのに、天井が見えるだけで、顔を横向けることもできず、その自分の横に座った人物を見ることができませんでした。そうこうしているうちに、再び寝てしまったらしく、目が覚めたときには、もう人影はありませんでした。
私にとっては幽霊らしきものの存在を体験したのは、そのときがはじめてでした。
さまざまな臨死体験などの本を読んでいると,死後の世界があるように思えますが、それらは脳内現象にすぎないという説が有力なように思われました。
ところが、数年前に出版された『プルーフ・オブ・ヘブン』は、その通説をくつがえす本でした。
『プルーフ・オブ・ヘブン』
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4152094087/oshoartunity-22/ref=nosim
この本の著者エベン • アレグザンダー氏は、29年間、脳神経外科・神経内科に携わり、アメリカの名門ハーバード・メディカル・スクールで准教授を務めた超一流の脳神経外科医で、これまで200本の論文を執筆し、研究者としても世界的に有名な科学者です。
彼は、重度の細菌性髄膜炎を発症し、7日間の昏睡状態が続き、回復の見込みがないとされ治療が打ち切られましたが、7日目に奇跡的に覚醒し、まったく後遺症もなく回復しました。
細菌性髄膜炎というのは、脳や髄膜に細菌が感染し、脳が破壊されていくという病気で、成人では1000万人に1人という、きわめて稀な病気で、致死率は90%にも達する病気です。
アレグザンダー氏は退院後、入院中のスキャン画像や、臨床検査や神経学的検査の所見など、すべてのデータを詳細に調べたところ、昏睡状態にあった7日間、彼の脳機能は完全に停止していたことが判明し、自分が訪れたのは「死後の世界」であると主張したのです。
常識では計りきれない不思議な世界というのはあるのかもしれません。
シュンニョは語ります。
「OSHOがすることのなかには、私たちをからかっているだけのことなのか、それともその場の状況を方便として使っているということなのか、それとも、それはほんとうに見かけどおりのことなのか、私にはまったく見わけのつかないこともありました。
たとえば幽霊の一件です。OSHOはたくさんの講話のなかで、「幽霊などいない、それは人間の恐怖の産物だ」と言っています。
彼はその一方で、幽霊の実在という考えに私が夢中になっているのも知っていました。
私は彼に「私は友好的な幽霊にしか出会ったことがないので、恐くはありません」と話したこともあります。
OSHOのそばではいろいろな状況が生まれますが、私がそうした状況とともにあるための唯一の方法は、それをこのうえなく真摯に受け止めることです。彼はこのうえなく真摯なのですから。
彼は幽霊や精霊について「私の睡眠が妨害されないかぎり、そうした霊のことは気にしない」と言いました。
彼が私を呼んで 「誰かが私の部屋に入らなかったか」と尋ねたことが何度かあったのです。
あるときOSHOはアナンドを部屋に呼んで、扉をすり抜けて部屋に入ってくる人影が見えたと言いました。
その人影は部屋を横切り、彼のベッドの前を通り過ぎ、彼の椅子の背後に立ち、それから彼の足に触れようとして、そしてふたたび扉をすり抜けて出ていったそうです。
「ゆっくり眠っていたのに、この霊のおかげで睡眠を妨害されてしまった」と、OSHOは言いました。
彼はまた「それは死者の霊なのかもしれないし、私のそばにいることを渇望している生きた人間の霊なのかもしれない」と言いました。
「それはチェタナかもしれない」とも思ったそうです。その人影は、私のような歩き方をしていたし、体型も私に似ていたというのです。
事実、OSHOの部屋の扉を霊がすり抜けていったという、ちょうどそのころ、私は眠っていました。
それは、とりわけ私を元気づけてくれる眠りでした。
半眠半醒の状態だったのですが、とてもくつろいでいました。
ですから、その霊は私だったかもしれないとアナンドから言われたとき、私は深く考えて「誰にわかるでしょう。もしかしたら、私がしたことかもしれないわ」と思いました。
私の肉体が休息しているあいだに、私の渇望が満たされたのかもしれません。その眠りのあとで、私があれほど元気になったのは、そのためだったかもしれないのです」
「和尚と過ごしたダイアモンドの日々」
(本書は絶版になっています。 お問い合わせはinfo@oejbooks.comまで)