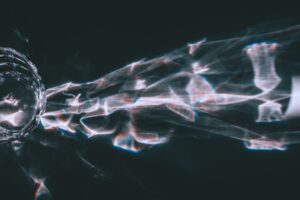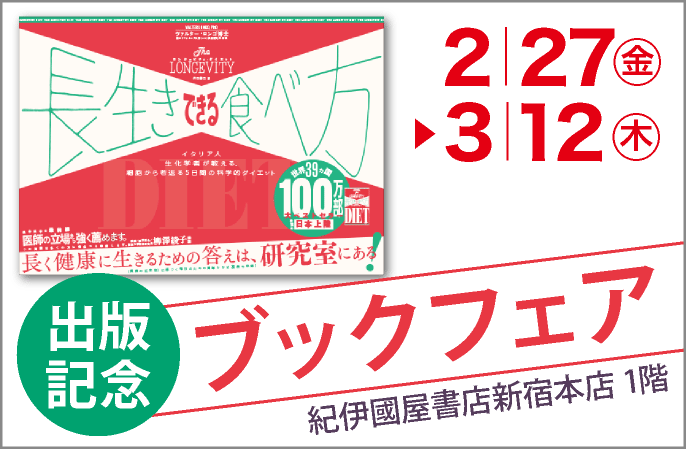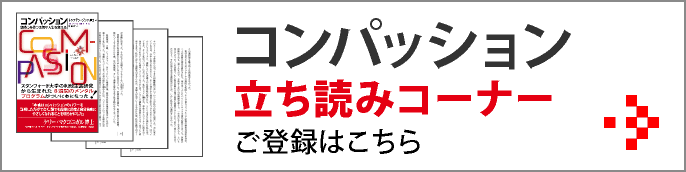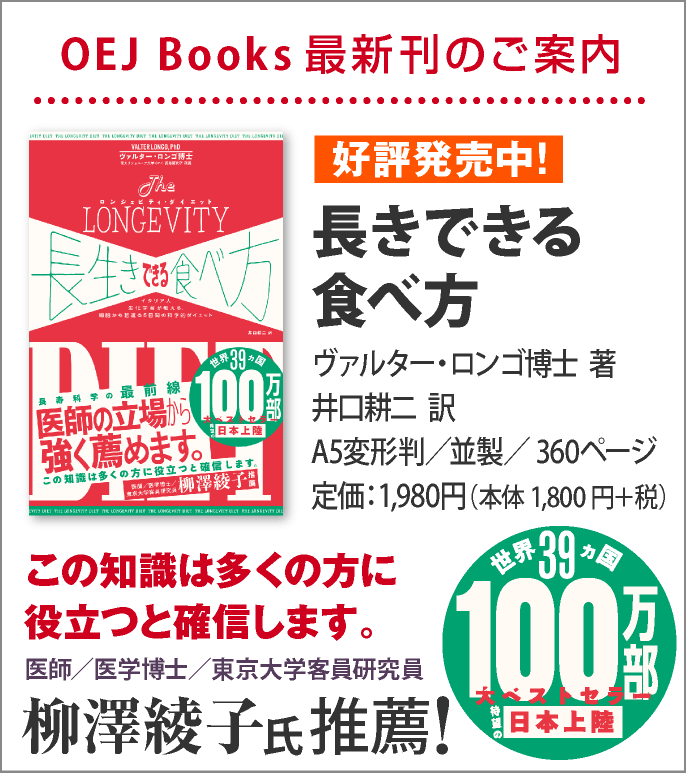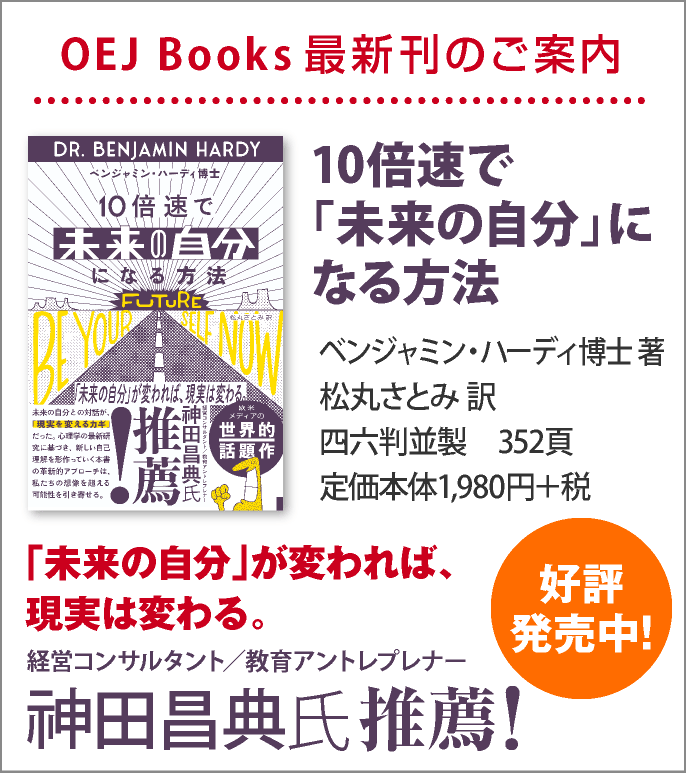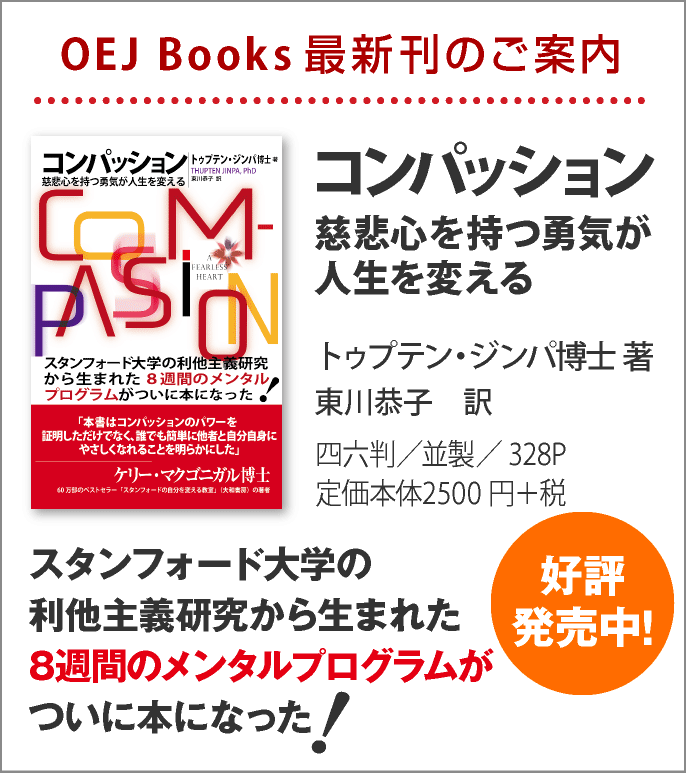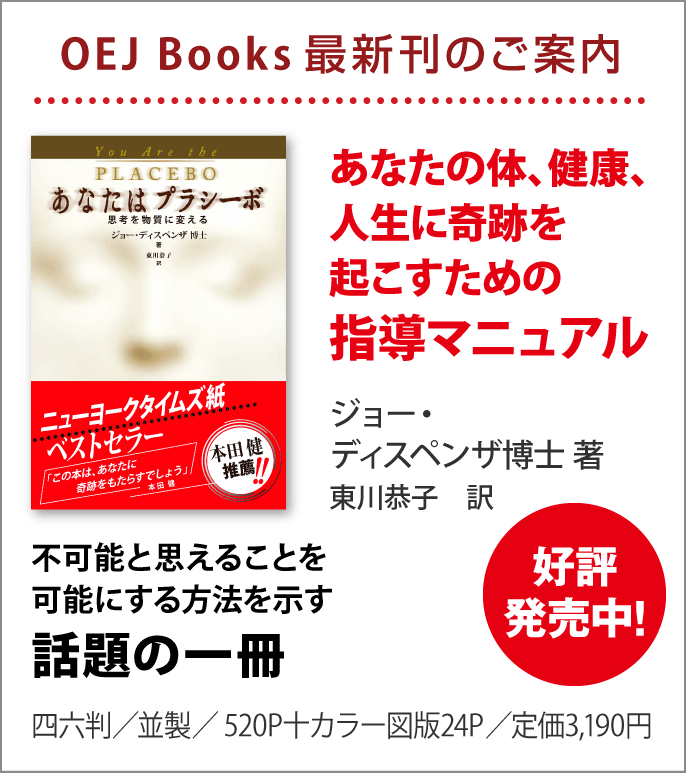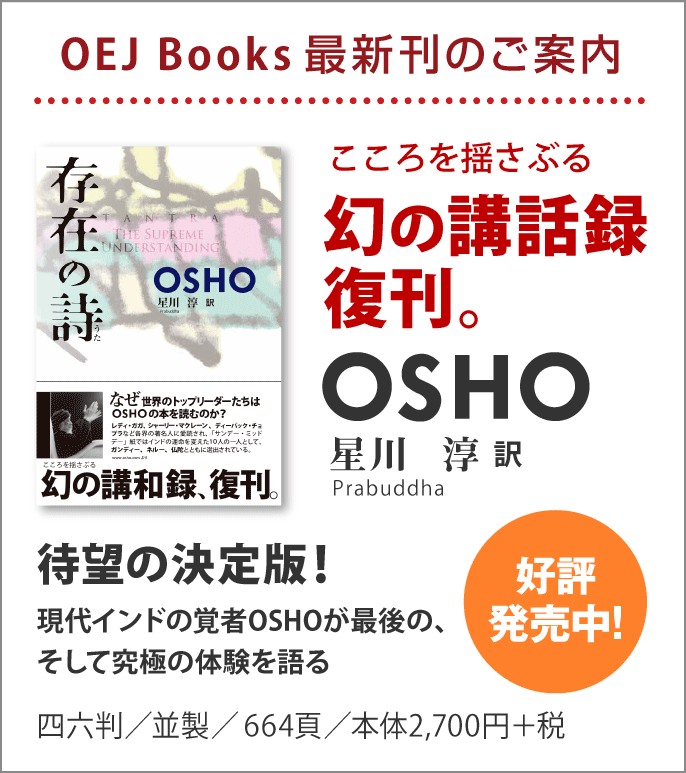OSHOがふだん、どんなふうにすごしているのか、ということはごく身近にその様子を見ていた人にしかわかりません。そんな日常の一端がここでは書かれています。
ウルグァイではプンタ・デル・エステという「南米のリビエラ」と呼ばれる風光明媚な海岸と知られる美しい場所に家が見つかり、OSHOはそこに滞在することになりました。
家は海岸の砂丘から歩いて3分ほどのところにあり、そのあたりの海辺の空気にはからだを癒す作用があると言われているところです。
シュンニョは書いています。
「この家に移ってきた日、OSHOは腰に両手を当てて歩きまわり、建物と庭をほめました。
それから2、3日すると、彼は毎日庭で座るようになりました。
ヴィヴェックに手をとられて階段を降り、プールのそばを通り過ぎ、彼のために庭に用意された椅子のところへと向います―――
そうした姿を目にするのはほんとうに大きな喜びでした。
ある日の彼は、私が「OSHOのパジャマ」と呼んでいた裾長の白いローブを着てあらわれました。
帽子は被っていません。
私たちが「OSHOのマフィアめがね」と呼んでいたカザール製のサングラスをしています。
そこにはくつろいだ雰囲気と、一風変わった趣がありました。
彼はときどきハシヤとジェイエッシュ、ときにはアナンドと打ち合わせをしました。
そうした用のないときのOSHOはただ座っていました。
ヴィヴェックがあらわれ昼食ができたと告げるまでの2、3時間、完全な静けさのなかで座っていました。
彼はなにも読みませんでした。
身体の向きを変えることさえなく、ただじっと座っています。
OSHOがプールサイドで座っているあいだ、私たちはみなじゃまにならないよう、そっと遠くに離れていました。OSHOのまわりにいると、彼のプライバシーを尊重したいという思いが自然にわきあがってきます。
OSHOがわざわざ口にだして私たちにそれを求めるまでもありません。
講話で私たちとともにあるとき、彼はほんとうにたくさんのものを私たちに与えてくれます。
ですから、彼が庭を歩いたり食事をしたりしているときは、まったくひとりのままにしてあげたいと思うのです。
OSHOが、たまたまどこかでだれかに出会ったときには、彼はその人に全身全霊をもってあいさつしました。
その様子は、ほんとうになにか特別なものでした。
彼は貫くような目を持って相手を見ます。
予期せずに彼に出くわしたときには、私は身体が震えました。
それでもやはり、彼のプライバシーは尊重するべきものとして感じられました。
ですから、私たちがOSHOと同じ家に暮らしていたといっても、講話をしていないときのOSHOは、ひとりで静かに座っていました。
アナンドからこんなことを聞きました。
ある日、アナンドが庭でOSHOのそばに座り、新聞の切り抜きや弟子たちからの手紙を読んであげていました。
すると海から強い風が吹いてきて、庭にそびえる背の高い松の木を揺らしました。
いくつもの松ぼっくりが石つぶてのように降ってきました。
ふたりのまわりに音をたてて降ってきます。
アナンドはOSHOを屋根の下に避難させようとしました。
ところがOSHOはまったく平然とした声で「いや、私にはあたらないよ」と言い、そのままゆったりと座っていました。
アナンドはまわりに降ってくる松ぼっくりのなかを飛んだり跳ねたりしていたのですが、OSHOは完全にくつろいだ様子。
そして「私にはあたらないよ」とほんとうにあたりまえのように言った彼の様子。
それがアナンドの記憶に残りました」
「和尚と過ごしたダイアモンドの日々」
(本書は絶版になっています。 お問い合わせはinfo@oejbooks.comまで)