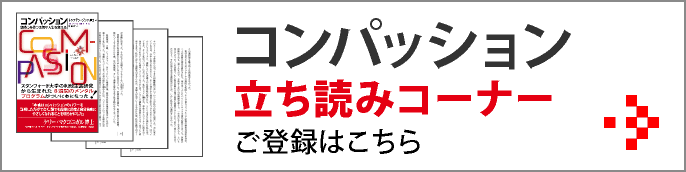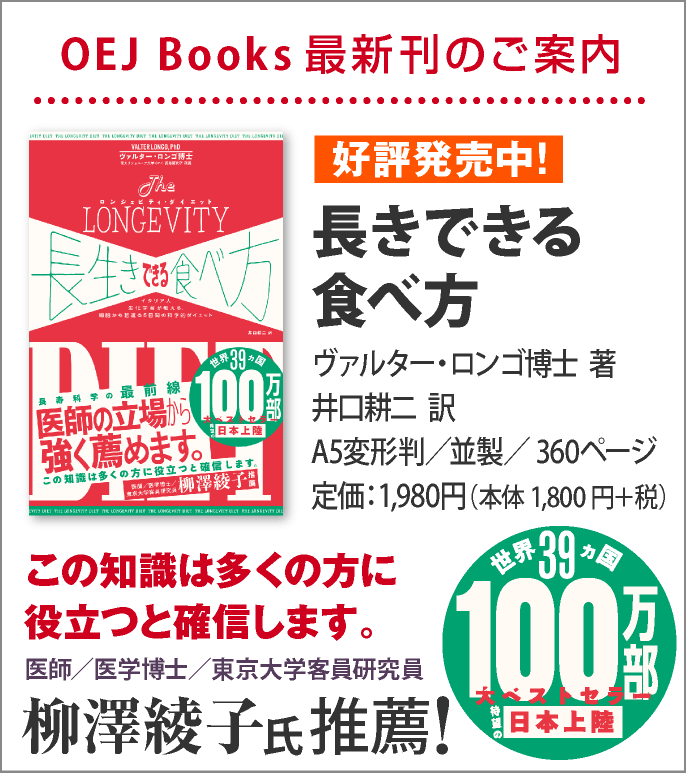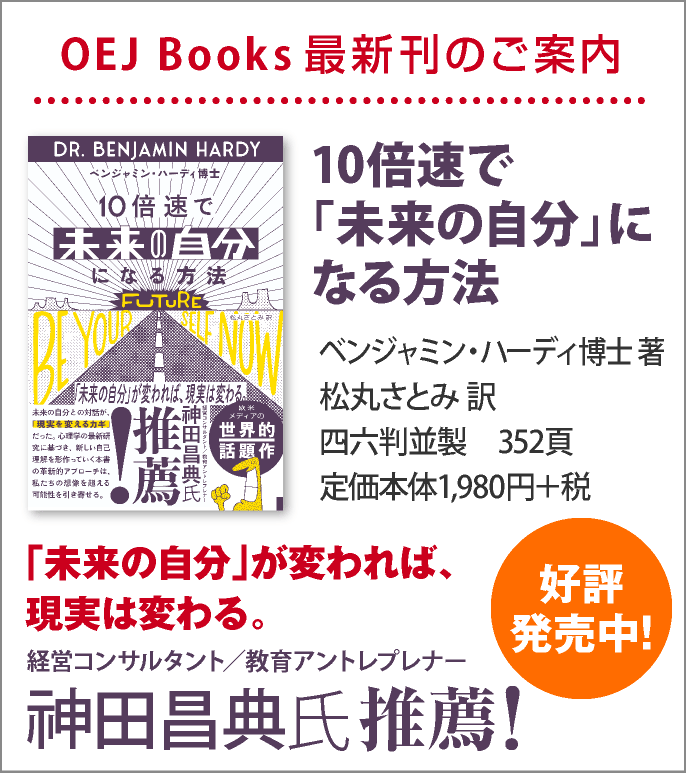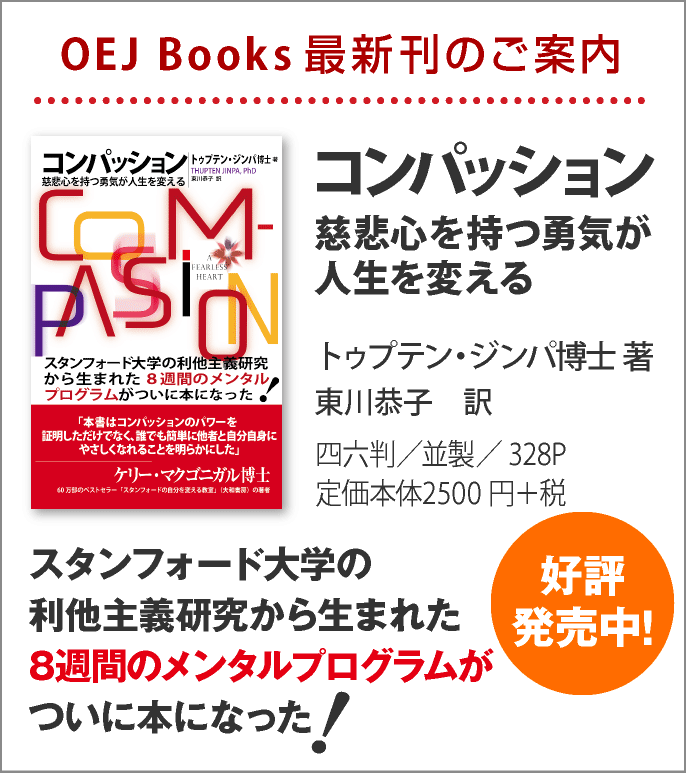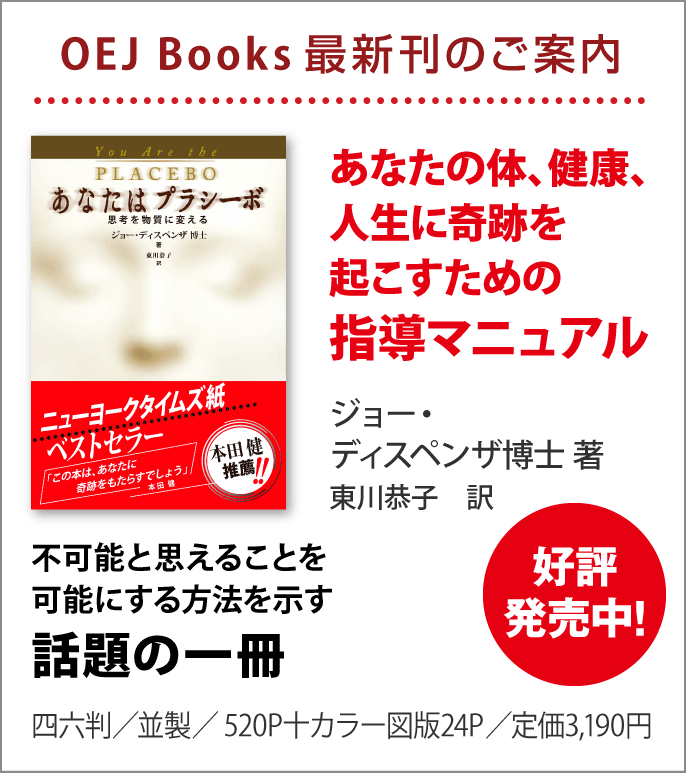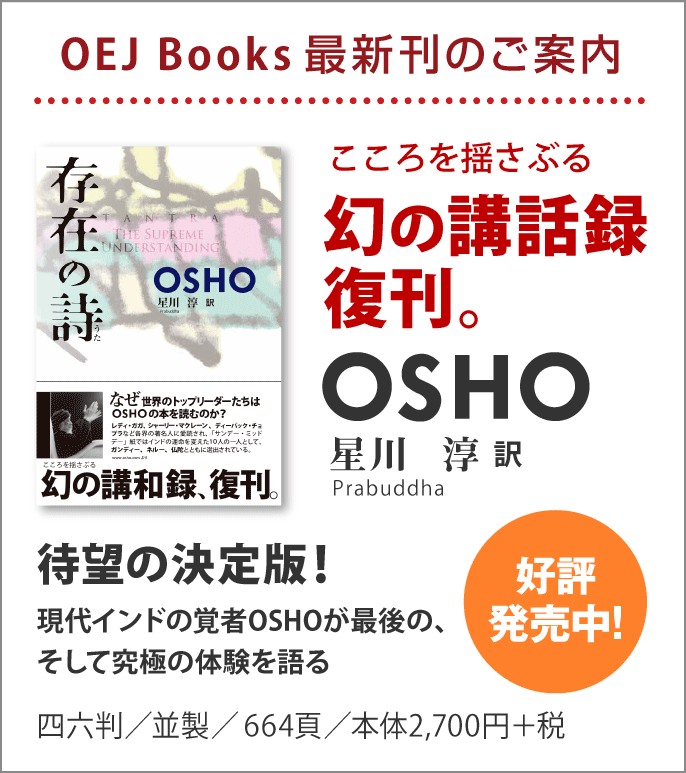いったんハートが関わったら、
何も問題とならない
時空や生死さえも、
いっさい問題にならない
いったんふたつのハートが
ひとつに溶け合ったら、
私が肉体を去ろうが、
あなたが肉体を去ろうが
たいした違いはない。
ときには肉体を持たないほうが楽でさえある。
なぜなら、肉体は常に足枷だから……
あなたがどこにいようと、
私には用意ができている。
ただひとつ重要なのは、
あなたが私に対して
用意ができていなければならないということだ。
Osho.
死を前にしたとき、人は無力です。
それを止めることはできないし、なすすべはありません。
人は、いつかはこの肉体を去っていかざるを得ない運命にあるのです。
その人への思いが強ければ強いほど、その別れは辛いものになります。
それは死んでいくものにとっても、残されるものにとっても同じです。
父を亡くしたときはそうでした。
それはまだOshoを十分知る前であり、肉体の別れがすべての別れでした。
しかしOshoを知るようになり、Oshoとともにいるようになり、肉体ではないつながりを感じることができるようになりました。
Oshoはあるとき「私の肉体だけを見るものは、私を見ていない。
私が肉体を去ったときに私を見失うだろう」というようなことを話すのを聞いたことがありました。
それを聞いたときにはその意味が分かりませんでした。
しかしOshoが肉体を離れたときに起こったことがまさにそれでした。
多くの人がOshoを見失ったようでした。
しかしハートで関わった人たちには、そこには目に見えないつながりが確かにあることが感じられるのです。
Oshoは自分が肉体を去ることを知り、そのための準備を整えていたのです。
それは後に残されるものにとってもそうでした。
後に残されるものも、Oshoが肉体を去ることが避けられないことを知り、そのこころの準備をしていたのです。
マニーシャは書いています。
『このところずっと、Oshoの具合は思わしくなく、
最後に彼を目にしてから、もう2ヶ月がたっていた。
ある友人に宛てて、こんな手紙を書く。
「おそらくこれは、最終段階だと思います。
Oshoが私たちとともにいられるのは、
あと1年か2年かもしれないというのが、私の個人的な思いです。
それは、醒めていながら痛みに満ちた思いですが、
彼が永遠に私たちとともにいられないのは現実です。
だから私たちはその考えに慣れて、
彼の存在が信じられないほど容易に私たちを満たしてきたものを、
今度は私たち自身の中に見出す必要があるのでしょう。」
1ヶ月後、私は別の友人にこう書く。
「いまのOshoの身体はぼろぼろです。
Oshoの主治医のア ムリットによれば、
彼の身体はこの1年か2年の間に20年寿命を縮めたに違いないとのことです」
「2年前、彼が講話を終えて荘子講堂(チャンツーオーディトリアム)を出て行こうとして、
危うく転倒しそうになったことがあります。
デヴァギートとニーラムと私が、同時に彼の椅子に駆け寄りました。
ニーラムが 彼のサンダルを、デヴァギートが彼の身体全体を支える一方で、
私は彼を支えるために思わずその手を握っていました。
そのあと、彼は真っ直ぐに立ち上がると、
両手を合わせたナマステの姿勢で、ゆっくりといつものように出て行きました。
私たちは全員、その出来事にショックを受けました。そして、いま……」
「彼の現在の状態は『詭い』という言葉で言い表せるでしょう」
4ヶ月たったいまも、和尚の健康状態は、私たちの前に姿を現すには悪すぎた。
私は、ある友人に宛てた手紙にこう書く。
「私たちは、本当に可能性を秘めた時期に入りつつあると思います。
これまで何年にもわたって、Oshoの言葉と臨在という極上の食べ物を一口ひとくち、
スプーンで与えられるという毎日を送ってきました。
そしていま、私か理解したことを生きるのは、私自身にかかっているのです」
それから再び、まったく思いもかけず、私は何年か前に起こったのと同じ体験ーー
数日間、すべてがあるがままで完璧に見えるという体験ーーをすることになる。
その体験の中で、内側に完全なる調和を感じ、
私のあらゆる人間関係と行動に、それが反映されるのを感じた。
自分の中に、用意のできた状態と、空間と、計り知れない虚空を感じる。
私という殻の中には、もう容易には戻れない。
漠とした、いささか切り離されたような感覚、
私は身体とは別の存在で、ただその中に住んでいるにすぎないのだという、明瞭な感覚がある。
私の人生や私を取り巻くすべてを、コントロールしたり方向づけたいという欲望も、そこにはまったくなかった。
この瞬間、この常に完璧な瞬間に優るものはありえなかった。』