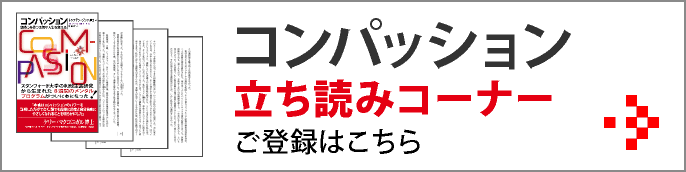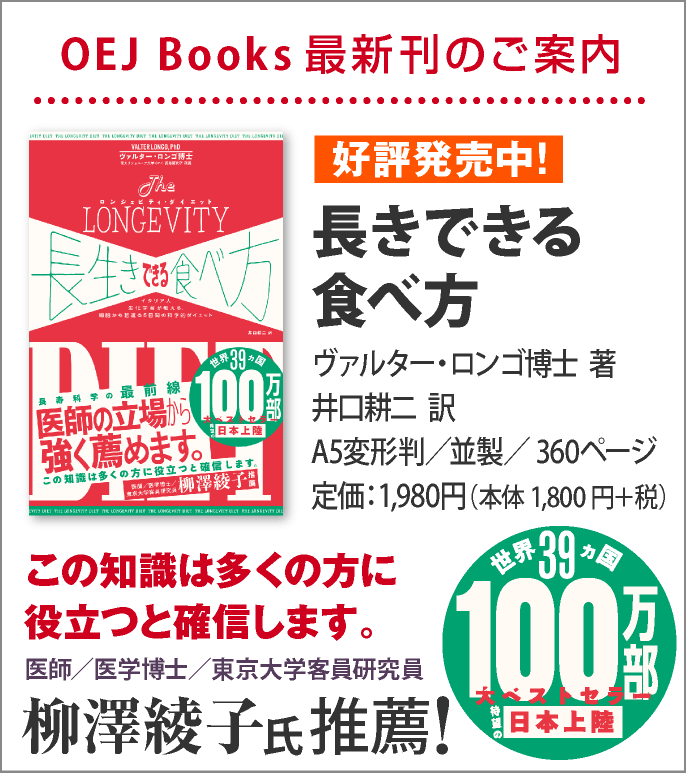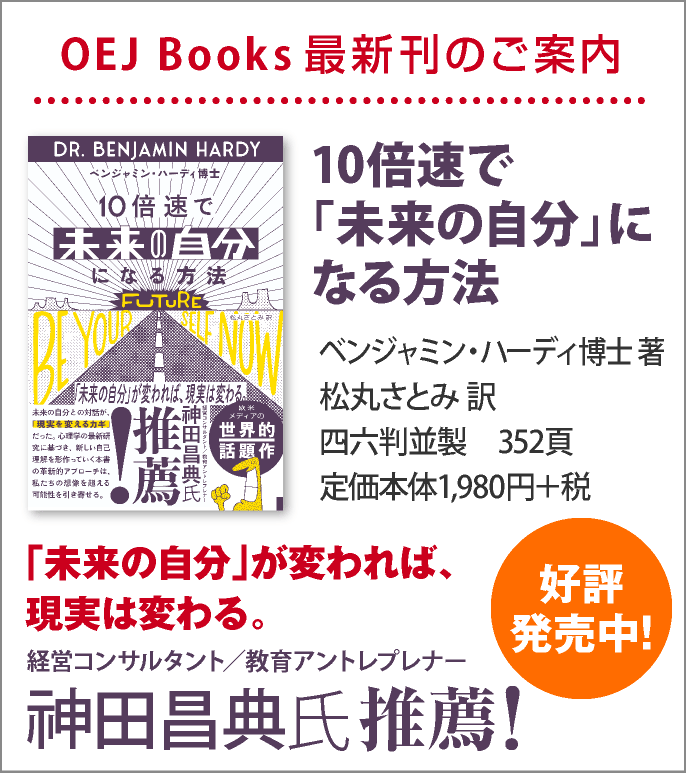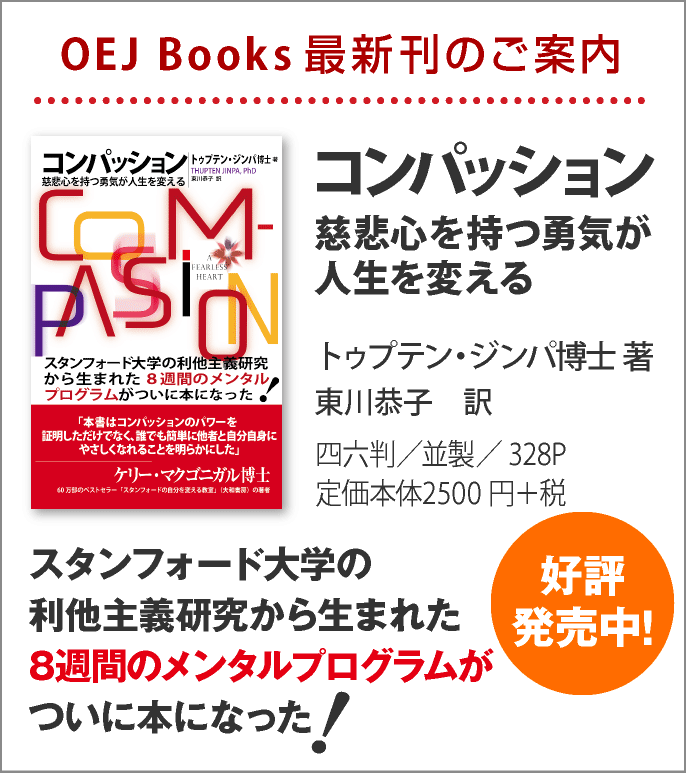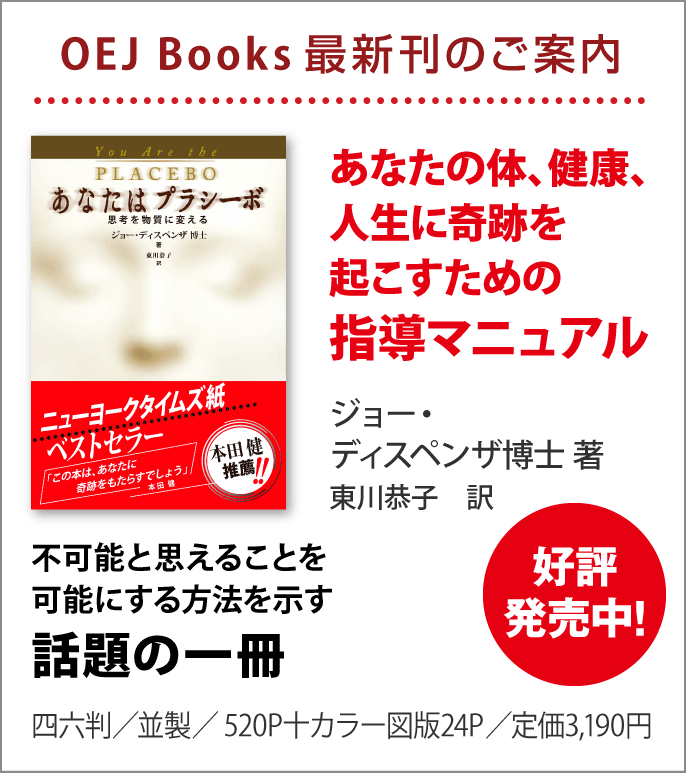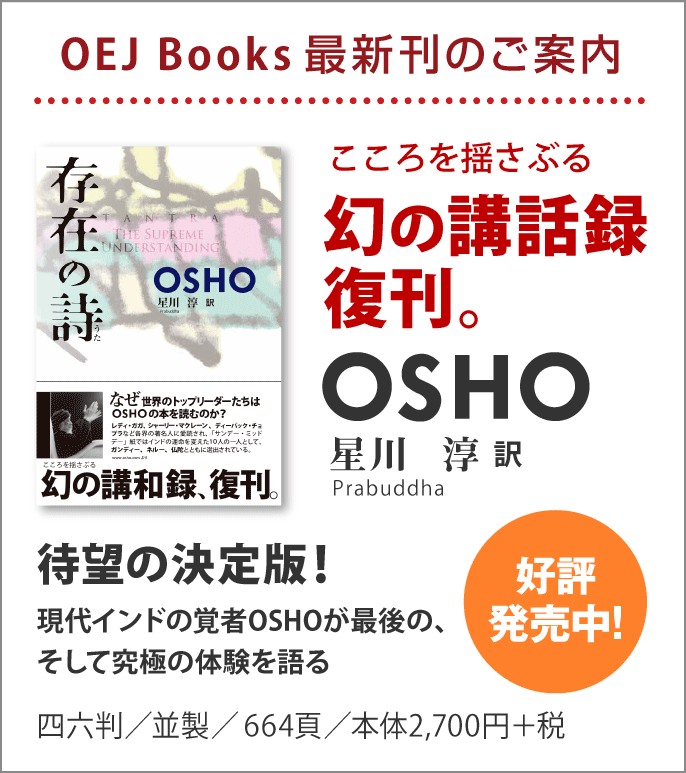マニーシャの「和尚との至高の瞬間」の本のいいところは、マニーシャの瞑想の実践が進むに連れて、彼女の瞑想の体験が深まり、それに応じて、Oshoの言葉への理解の深まりも私たちに示してくれるからです。
瞑想にはそれぞれの段階が人それぞれにあり、また、Oshoの言葉もその時々に応じた、その人に対する答えなので、一般的な、普遍的な回答ではありえません。
従って、Oshoの講話や言葉を聞くときにも、何がそのときの自分に合っているのかを見分けることが必要になってきます。
前回のブログで、Oshoはある少女に次のように回答したときのことを紹介しました。
「ある晩のダルシャンで、青白い、真剣な面もちの英国人の少女がOshoに、自分は神を探求していると言う。
それに対し、Oshoは微笑みながら、「我々は神ではなく、幸福を探し求めている。だが幸福を求めていると言えば、利己的に聞こえる。『神』はより受け入れやすいレッテルであり、より宗教的に聞こえる」と語る。
彼女は侮辱されたと感じているらしい。彼女が自分は本当に神を求めていると感じており、自分の探求がそれ以下のものだと言われるのを嫌悪しているのは、明らかだった。」
そのOshoの答えでさえ、その少女は受け取ることができず、自分が侮辱されたように感じたのでした。
しかし、Oshoがそのとき言わなかった(言えなかった)更なる答えがあったのでした。
その境地は宋時代の詩人、蘇東坡は「柳は緑、花は紅、真面目」と詠じ、禅の悟りの境地ともされています。
そのことをマニーシャは次のように語っています。
「何年かを経ていま、かつてないほどの歓びを感じている。そしてまた、エクスタシーはたしかに魅力的だが、終点ではないことを思い出す。
神—もしくは幸福——を探し求めていた、あの少女にOshoが言わなかったことは、悲しみと幸福の両方を越えた領域があるということだ。
それが瞑想の領域であり、そこには歓喜の体験さえもなく、ただあるがままの存在がある。
そして、私は自分が行動したり考えたり感じたりすることを観照できれば、あるいはそれらと同化せずにいられたら、またいつでもその領域を体験できる。
私が意気揚々となり、その意気に完全に捕らわれたとき、必ず次に反対の方向への振り返しがやって来る。もしエクスタシーと同化したなら、必然的に苦悩とも同化する。
Oshoに出会うまで、私はこれらを単に分かちがたい生の一部だと受け止めていた——人はその上昇と下降を、できるだけうまく乗り切ろうとする。
下降を避けるコツを知っている人々もいるようだが、私は知らなかった。
小さな悟りを通して、私は高揚感や悲しみを越えたところにある状態を味わった。
この出来事の中で私の意識と体、心の間の繋がりが壊れたか、もしくは緩んだかして、私は生をただ在るがままに見た。……花は美しいのではなく、ただ花そのものだった」