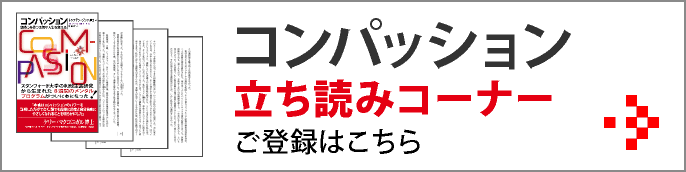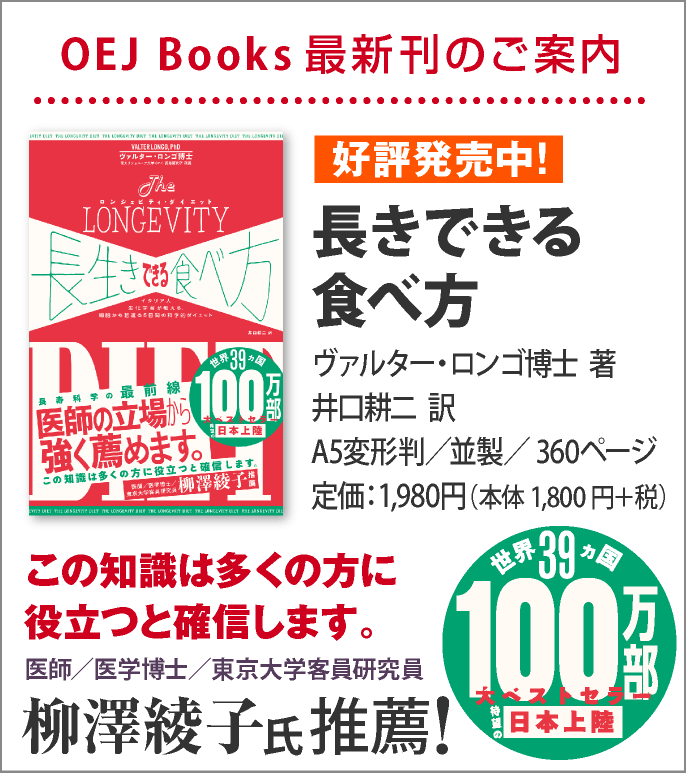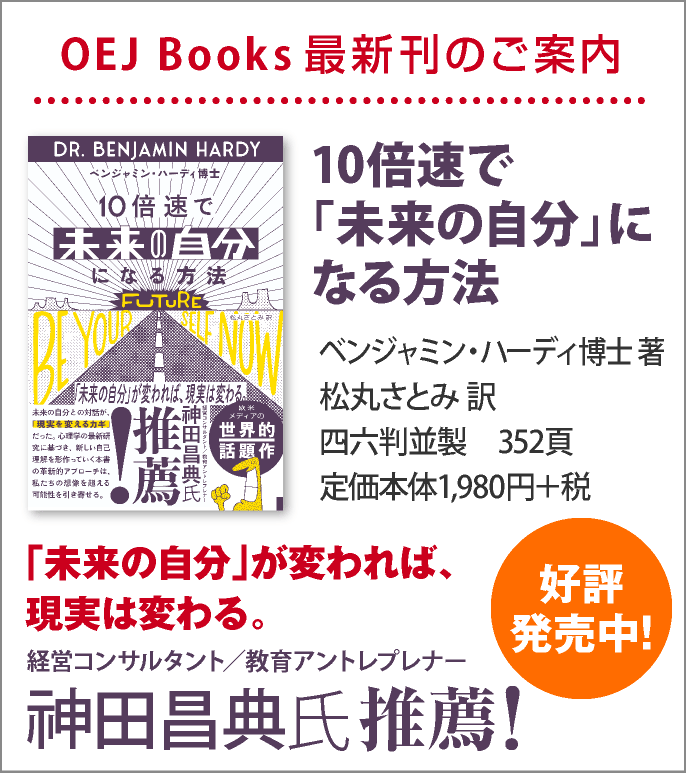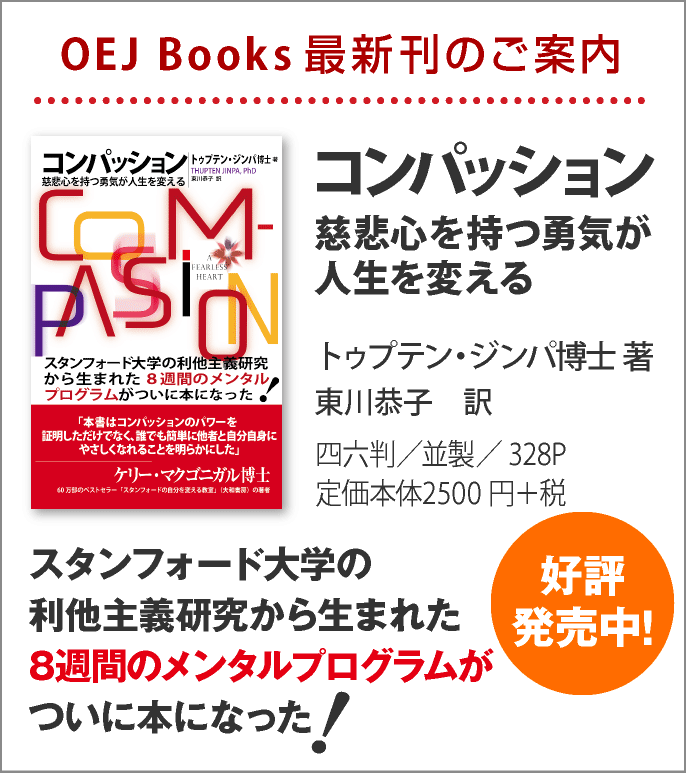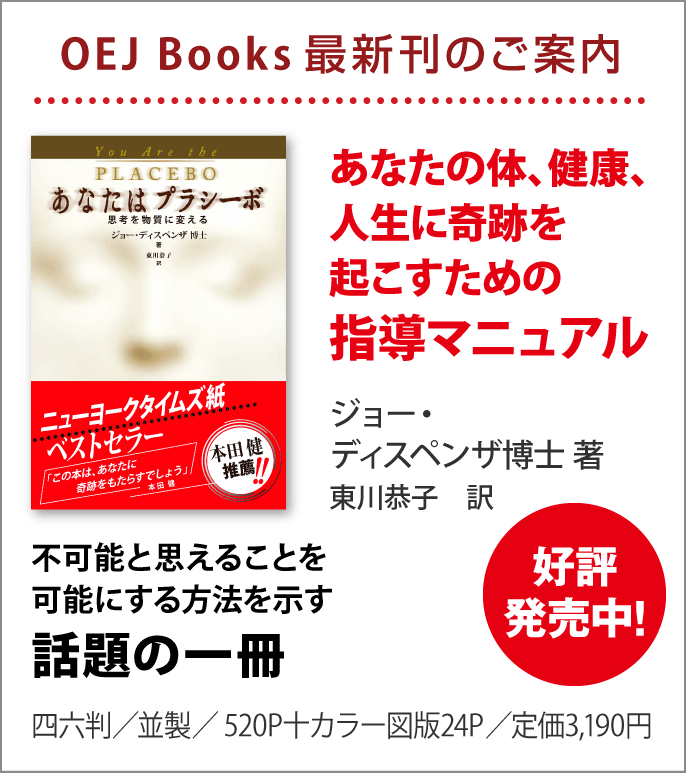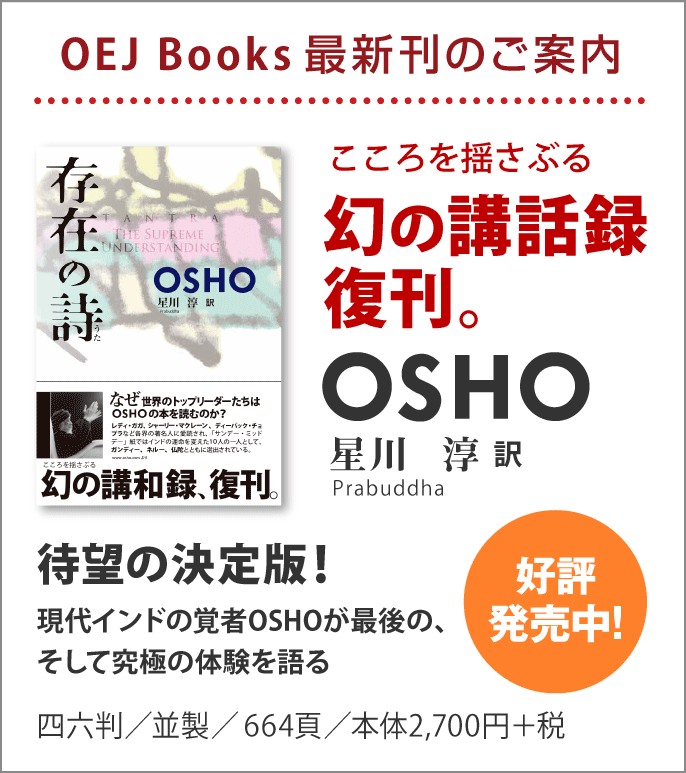OSHOの講話とともにあることは不思議な空間でした。
最高のエンターテインメントであり、最高の深み、高み、静寂と沈黙の体験でもありました。ありとあらゆる体験が凝縮されていた空間でした。
OSHOのこの時期の講話では、シュンニョが書いているように、ほんとうに消え入りそうな声で講話がはじまっていた時期がありました。大丈夫なのだろうかと思っていると、話しているうちに、いつものとおりの力強い声に戻っていくのでした。
いつもOSHOの講話は、どこからそのような言葉が湧いて出るのだろうと不思議でした。それだけの言葉を話しながら、彼が目指していたことは沈黙であり、静けさの空間だったのです。
それは、まさしく禅でした。
道元なども、「不立文字」「只管打坐」と言いながら「正法眼蔵」のような膨大な書物を著したり、臨済禅ではマインド(頭)の考えを切り落とすために公案のような禅問答をしていたり。多くの言葉や問答がありながら、そこには沈黙の空間があったのです。
生きたマスターとともにいることは、まさにその一瞬一瞬が矛盾であり、新しい発見であり、未知なる空間でした。そのOSHOが肉体に居続けるということは奇跡に満ちたことでもありました。と同時にOshoにとっては、苦痛に満ちた肉体に居続けることは、拷問のなかにいるようだったです。
講話のために、私たちの前に姿を現してくれるということは、ただただ、私たちへの慈愛だったのです。
シュンニョは語ります。
『病気でしばらく休んだあとで、ふたたび講話に現れるときのOSHOは、とても壊れやすく見えました。
私たちから何光年も隔たったところに行ってきたように見えるのです。
それなのに、話をはじめてしばらくすると、彼はだんだん力を取り戻しました。OSHOの声がしだいに力強くなっていくのが、はっきりとわかりました。そして講話を再開してから2、3日後には、彼はまったく別人のようでした。
「あなた方に話すことで、私は肉体に留まっている。私が話すのをやめたなら、その先はそれほど長くは生きないだろう」と、OSHOはいつも言っていました。
講話中の彼は、とても力強く見えて、病気だとはなかなか信じられないほどでした。
でも、彼に力がみなぎるのは、一日のなかで講話の時間だけだったのです。私たちの前に現れて講話をするために、彼はすべての力を蓄えていたのです。
講話で話したことについて、あとからOSHOがあれこれ言うのを聞いたことは、私には一度もありませんでした。彼の言葉はまるで空から湧いてくるようで、彼の記憶にはなんの痕跡も残さないかのようでした。
ところが、ある晩にかぎって、講話を終えたあとにOSHOが「ある点について、伝えたいことをあまり明確に伝えられなかったと思うのだが」と私に言いました。
そして彼は、講話のあるところについて、ふたたび話してくれましたので、私はそれに、もういちど注目することになりました。それはつぎのようなものです。
舞台の上ではすべてが演技だ。
舞台の上ではすべてがたんなるドラマにすぎない。
舞台の裏には純粋な静けさ。 無。休息。くつろぎ。
すべてが完全な静寂へと向かう。
彼は禅について話すようになりました。
もっとも彼は、話すことよりも沈黙に満ちた雰囲気を生みだすことに重点をおいていました。
彼は、ひと言ひと言を句切りながら「……」の沈黙「……」というように話しました。
そこにある沈黙そのものを指さすようにしてです。
あるいは彼は、しばらく無言のままにとどまり、高く伸びた竹のきじむ音、雨音、落葉を舞い散らす風の音など、まわりのいろいろな音に私たちの注意を向けました。
「聞いてごらん……」
と彼が言うと、巨大な沈黙が降りてきて、ブッダホールをすっぽり覆うかのようでした。』
「和尚と過ごしたダイアモンドの日々」
(本書は絶版になっています。 お問い合わせはinfo@oejbooks.comまで)