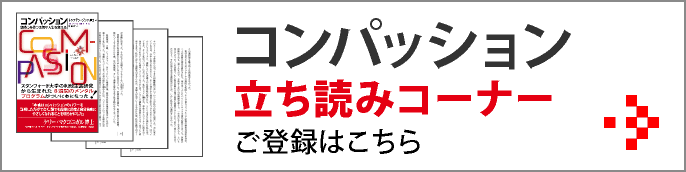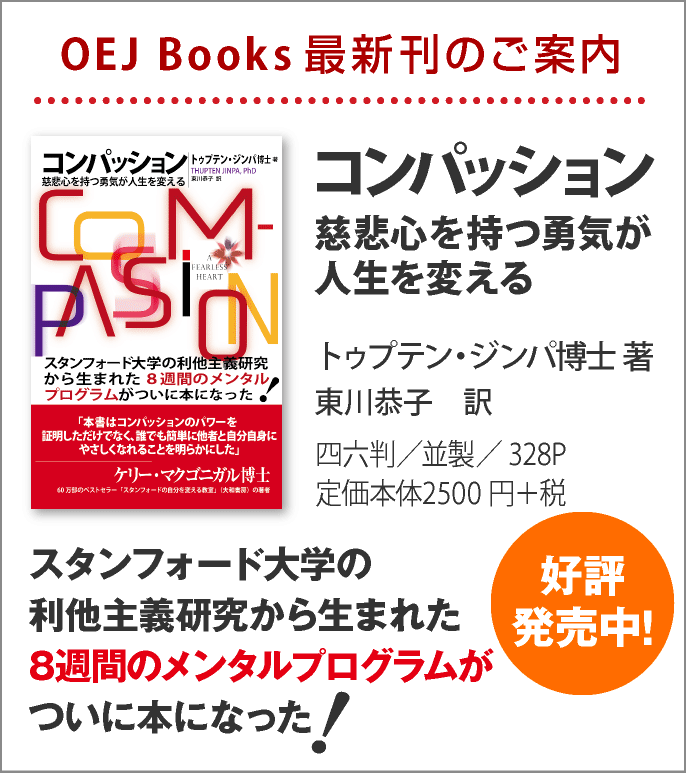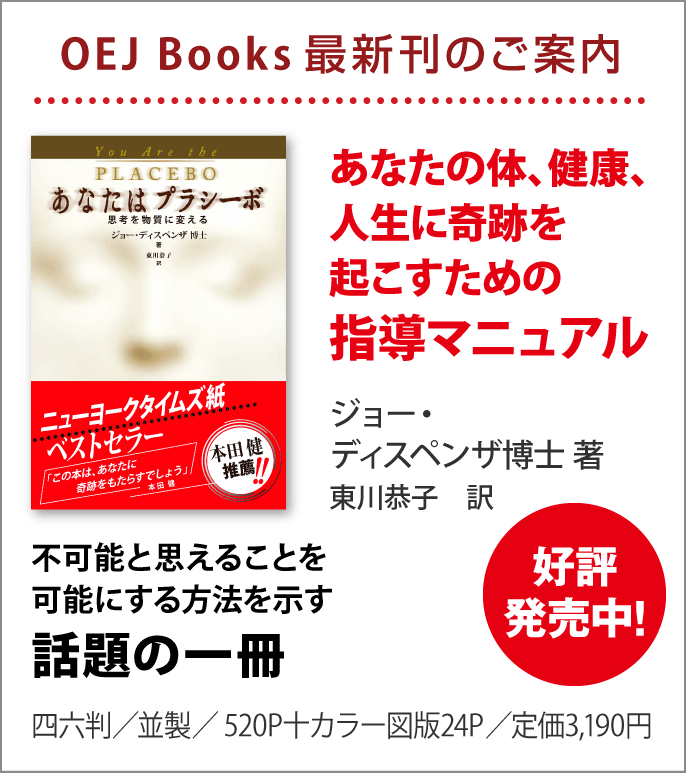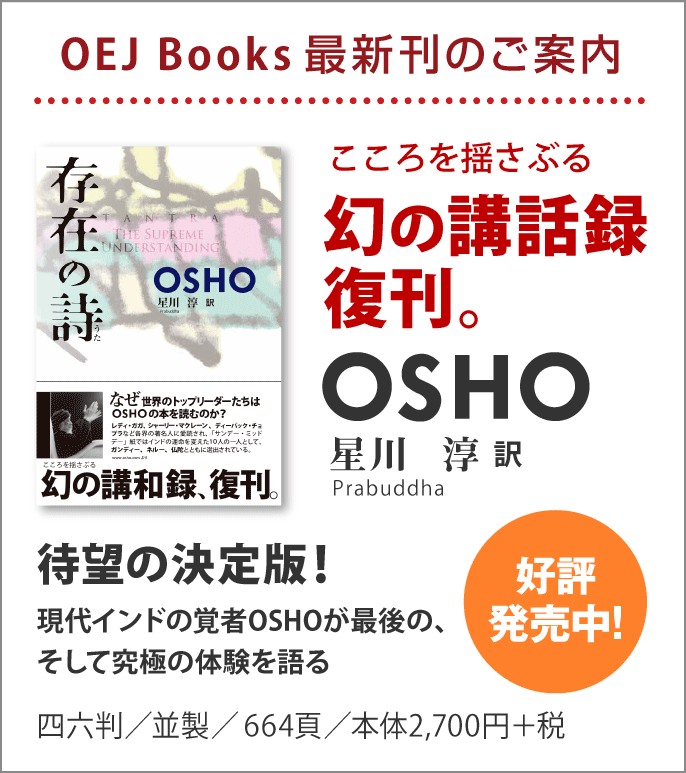OSHOの言葉はとてつもないパワーを持っています。
その言葉は詩的であり、話す言葉や言葉の波動は、まさにその言葉のエネルギーを伝えるもので、言葉の内容がわからなくても、声を聞いているだけでもその話の波動を伝えてくれます。
Oshoヒンディー語の講話を聴くこともありますが、意味が分からなくても、その声を聞いているだけでもOSHOの愛の波動を感じることができて心地よいものです。
愛を語るときには愛の波動を、真理を語るときには真理の波動を、OSHOの悟りの体験を語るときにはその悟りの体験が言葉の波動とともに伝わってきます。
しかしOSHOが叱ったときというのは、身体が硬直するほど怖いものがありました。
一度だけ講話で、ある質問者があまりにも無意識な質問をしたので、OSHOは「この質問をした人は立ちなさい」と強い口調で言ったことがあります。
その「スタンダップ!」という声を聞いたときには、まさにそう言われて立つ勇気を持っている人はいるんだろうか、と思えるほどでした。
もし、私がそういうふうに言われたとしたら、足がすくんで立てなかったでしょう。
自分でなくてよかった、と心から思いました。
そのOSHOの言葉のパワーを知っているので、この爆弾宣言を話したときのOSHOの講話の場にいなくてよかったと、この箇所を読んでいるときに思ったほどです。
ですから、シュンニョが、この講話を聞いたときに、「『拍手しなさい!』とOSHOが叫んだとき、まるで爆弾が炸裂したかのようでした」と書いているのはとてもよくわかります。
あの「スタンダップ!」と言う声が聞こえてきそうですが、今回のOSHOの言葉は、それにも増して強烈なものだったと思われます。
今回のOSHOの講話は、それまでのコミューンでのできごとについての、自由と責任ということを突きつけられた瞬間でもありました。
それはそうです。
OSHOは3年半の沈黙を破って、それらのすべてに対応しなければならなくなったのだし、それはまさにコミューンメンバーがすべてを引き受けるべきもので、OSHOひとりに任せておくべきものでもありません。
そのことについても無意識であった現状が暴露したのですから。
シュンニョは語ります。
「1985年10月8日、OSHOは講話でこう語りました。
「・・・私が赤い服とマラを捨てるように言ったとき、あなたがたは拍手した。
拍手しながら、それがどれだけ私を傷つけていたかに気づいていなかった。
それはあなたが偽善者だったことを意味している!
赤い服を捨てるのがそんなにうれしいなら、なぜ赤い服を着ていたんだね?
なぜマラを着けていたんだね?
私が「捨てなさい」と言ったとき、あなたがたは大喜びだった。
そして、みんなはブティックに押し寄せて服を替え、マラも捨てた。
あなたがたは、拍手したことで、服を替えたことで、どれだけ私を傷つけたのかわかっていない。
私は、これからもうひとつのことを言わなければならない。
そしてあなたに拍手する勇気があるかを見てみたい。
それはブッダフィールドがなくなるということだ。
だから、光明を得たいならば、ひとりでワークしなければならない。
ブッダフィールドがなくなるのだから。
自分が光明を得るためにブッダフィールドのエネルギーに頼ることはできなくなる。
さあ、せいいっぱい拍手するがいい。拍手しなさい!
これであなたがたは完全に自由だ。
光明を得ることに関してさえ責任があるのはあなたひとりだ。
そして、私はあなたから完全に解放された。
あなたは白痴のようにふるまっていた!
そしてこれは、どれだけの人たちが私と親しい関係にあったかを知るためのいい機会だった。
そんなに簡単にマラを捨てられるなら‥‥‥。
私の家に住むサニヤシンのなかにさえ、大喜びでたちまち青い服に着替えた者がひとりいた。
それから何がわかるかね?
赤い服は重荷だったということだ。
彼女は自分の意志に反して赤い服を着ていたのだ。
だが、私はあなたに、あなた自身の意志に反することは何もしてほしくない。
今の私は、あなた自身の意志に反してあなたを光明へと導くようなことさえもしたくない。
あなたは完全に自由だ、自分の責任は自分でとりなさい」
「拍手しなさい!」とOSHOが叫んだとき、まるで爆弾が破裂したかのようでした。
私たちは灰に覆われ、身を硬くして座っていました。
講話のあと、私は顔を赤くはらし、すすり泣きながらマンディールの外に出ました。
最初に見かけたふたりの友達のところに行き「助けて、助けて」と言いました。
私はそのふたりと日のあたるところでコーヒーを飲みました。
それは、それまでの4年間に私たちのふるまいが頂点に達した瞬間のようでした。
シーラのしたことに対する責任は、私たち全員にあったのです。
私の問われるべき責任とは、なにも言わなかったことでした。
愛きょうのあるやさしい人でいるだけでは不足でした。
私には、自分の英知と理解を育て、自分で感じていることを口にする勇気を身につける必要がありました」
「和尚と過ごしたダイアモンドの日々」
(本書は絶版になっています。 お問い合わせはinfo@oejbooks.comまで)