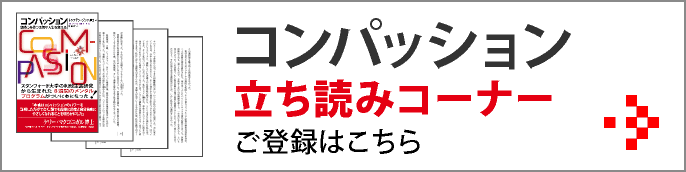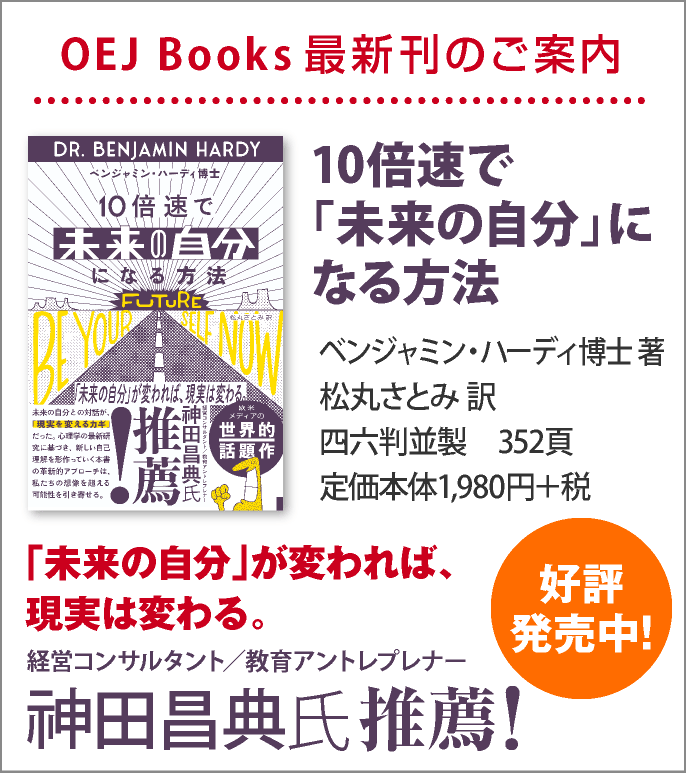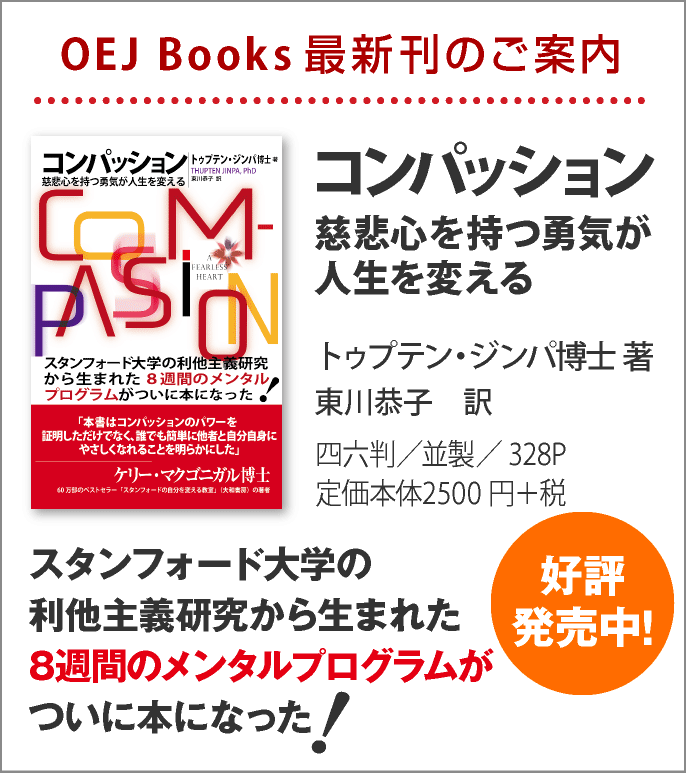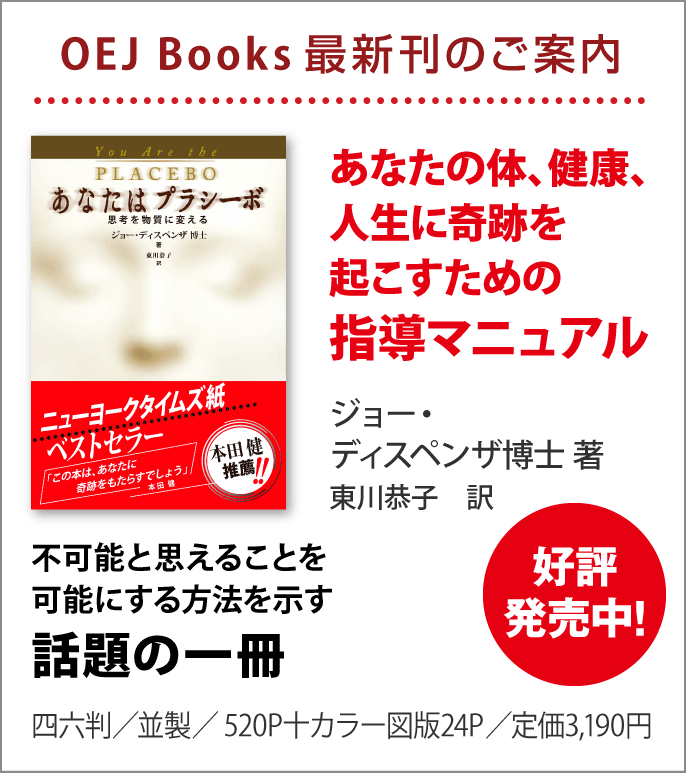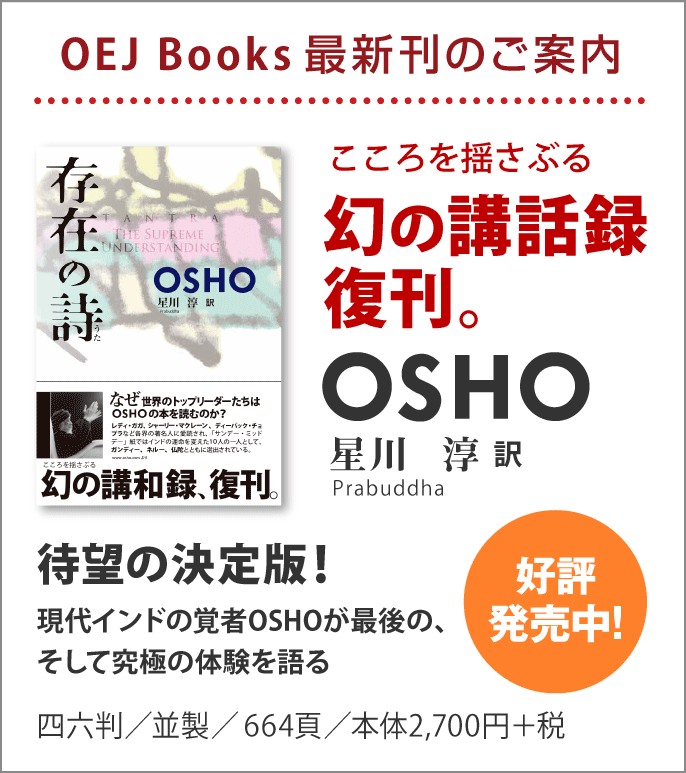瞑想というのは、テクニックではないし、体験でもないというふうに言われています。
瞑想をすることはできないし、ただそれは起こるだけだ、と。瞑想は、その起こるための環境を準備することができるだけだ、と。
なぜなら、もしそこに瞑想するということがあれば、そこには瞑想している人(エゴ、マインド)がいることなるし、瞑想の体験があれば、そこにはそれを体験している主体があることになるからです。
瞑想とはそういうエゴや自己を超えたものなのです。
瞑想は努力したからといって起こるわけではないし、努力が逆に妨げになることもあります。
かといって、その努力がそれが起こる環境を作ることもあるし、あるいは全くのアクシデントとして、予想もなく突然偶然にもそういう境地が起こってしまうこともあります。
マニーシャの幸運なところは、そういう突然の悟りの一瞥を体験したり、あるいはまた自分の瞑想のプロセスをいつでもOshoに質問して、Oshoがそれにアドバイスを与えているところにあります。
瞑想をする人にとってマスターが必要だというのはまさにこういうところにあるのです。
そしてOshoはそのときの弟子にアドバイスを与えるだけではなく、直接Oshoに接することのできない弟子たちにもアドバイスを与えつつ、かつまた未来の弟子たちにもアドバイスを与えていたところに彼のワークの複雑さがあります。
法華経などを読むと、お釈迦様が説法をすると、突如として地湧の菩薩が出現して、お釈迦様の話を聞くという場面があったりまします。
Oshoは講話のために現れてきたときに、合掌(ナマステー)をしながらそこに集まっている人たちに挨拶するのですが、集まった人たちだけではなく、空中やあらぬ方向にまで合掌をして挨拶しているように思えることがあって、そういうときには法華経のその場面を思い出したものです。
何か目に見えない存在までもがOshoの講話を聴くために集まっているのではないかと思われるようなときもありました。
そのOshoの講話はそのときに聞いていた聴衆だけではなく、未来においてOshoの講話を聴く人たちにも向けられています。
そしてこのようにマニーシャが残してくれているOshoとの瞑想の記録は、マニーシャと同様に瞑想のプロセスを歩む人たち、「観照」とはなにかということを実習している人たちの手引きともなるものです。
マニーシャは語っています。
「探求とは自分が誰であるかを知ろうとすることだ、とOshoが言うのをしばしば耳にしてきた。
もしあなたが以前の私に「自分が誰なのか知っていますか?」と尋ねたなら、たぶん私とは、私がしたり考えたり感じたりすることの合計だと、答えただろう。
しかし、自分自身が働いたり話したり食べたり歯を磨いたりするのを観照し始めると、疑問が浮かんでくる。
私とは、単にここにあるマンゴーを食べたり、歯を磨いたり、考えたり、愛や憎しみを生みだすだけの者であるはずがない。
もしそうなら、自分自身が果物を食べたり、歯を磨いたりするのを観照する能力を持っているはずはない。
私が誰であるかということに関しては、確信が深まるどころか、それは徐々に薄れてくる。私が誰でないかということだけが、わかり始めている。
どこかが、何かがおかしいと感じ、自分が誰だかわからなくなることへの不安について、Oshoに質問の手紙を書く。私か誰かであるにしても、いまの私が言えるのは、せいぜい自分が大きくてフワフワした雲のように感じられるとも書いた。
それに対して、Oshoがこう言ったのを憶えている
――これこそ、人が真実を見出す方法だ。
自分自身だと想像していたすべては、落ちていきつつある。それはよいことだ。なぜなら本物が現れるためには、偽物を落とさなければならないのだから。
Oshoはこう言って私を勇気づけた。
「あなたはまったく正しい道を行っている。一度も道を間違えなかった。本物でないすべてを、ただ溶かし続けなさい。雲のように感じるのは、素晴らしいことだ。観照そのもののように感じるのは、素晴らしいことだ」
このことがあって数年後、ある日の講話中、突然に私はまったくの静止と沈黙のスペースに入る。
観照がまったく自然で容易になり、観照者であろうとするそれまでの努力はもはやなく、ただ観照のみがある。
Oshoの言葉と言葉の狭間の沈黙の中、鳥たちが最後の合唱を終え、こおろぎが子守歌を歌いながら眠りにつき、汽車はきしみながら走るのをひととき忘れて、物思いに沈んでいる。
リキシャの往来や警笛も、奇跡的に一時止んでいる。私の静止した体と心から何も入力されないとき、そこには私自身を定義できるものは何も残されていない。
私が存在することを証明するものは何もない。
「私は存在する。なぜならあの音を聞いているのだから。「私は存在する。なぜなら私は足を動かす必要を感じているから」とか、「私は存在する。なぜならあの音を聞いている私自身を見つめているのだから」とさえも言えない。
――なぜなら、それら外界の刺激が、いっさい存在しないのだから。
このスペースは、絶え間なく解説したり定義したり抑制したり、コントロールしたりする必要性を持つマインドから、完全に切り離されている。
これは、マインドの存在しない意識だ。
それは観照している者でさえなく、観照そのものだ。
しかし、これこそもっとも根本の、もっとも本質的な私であるように感じられる。
すなわち私とは、名詞などではなく、動詞なのだ!
どうしてこんなことがありえるのだろう? 私は何かを失ってしまったのかしら? 私自身を? いったいどうして「私」が不在なのに、この観照という動きのない活動は存在するの?
講話の中で、Oshoは私の疑問にこう答える。
「これはまさに正しい。観照する者は存在せず、観照のみが存在する。
意識のみが存在し、それは人格も伴わないし形も持たない。
そこに在るのは、どこからともなく現れ、どこへともなく消える炎のような気づきだ。
消えてしまうまでの間だけ、あなたはその炎を見る……。
あなたがいなくなる瞬間、観照は純粋なものとなり、この観照が途方もない祝福をもたらしうる」
「この観照こそ仏陀だ」