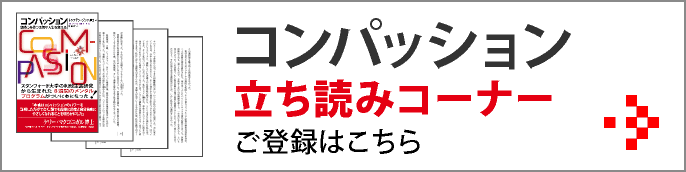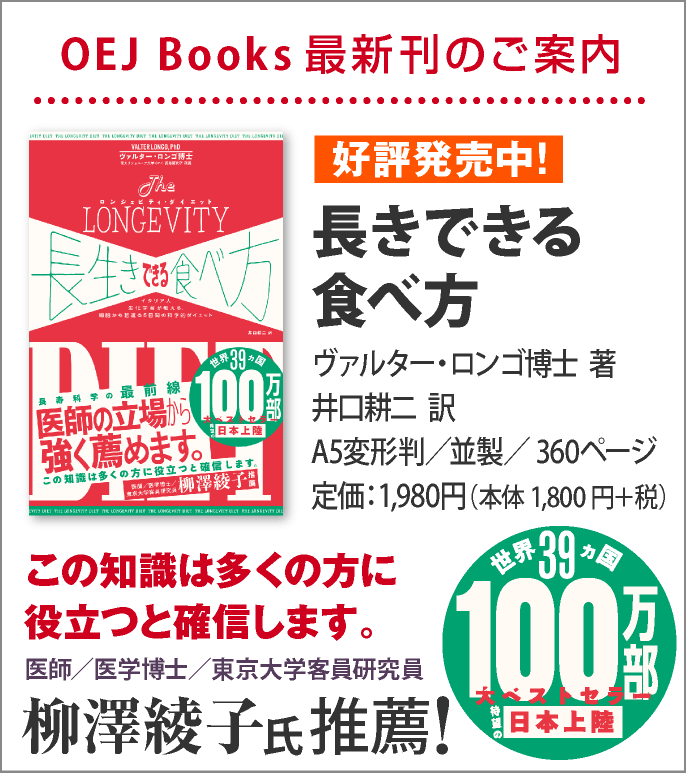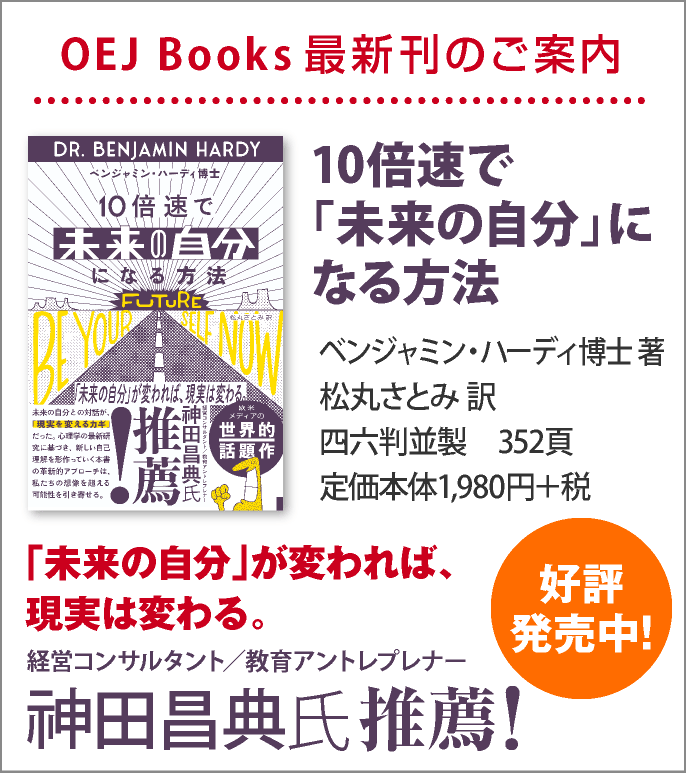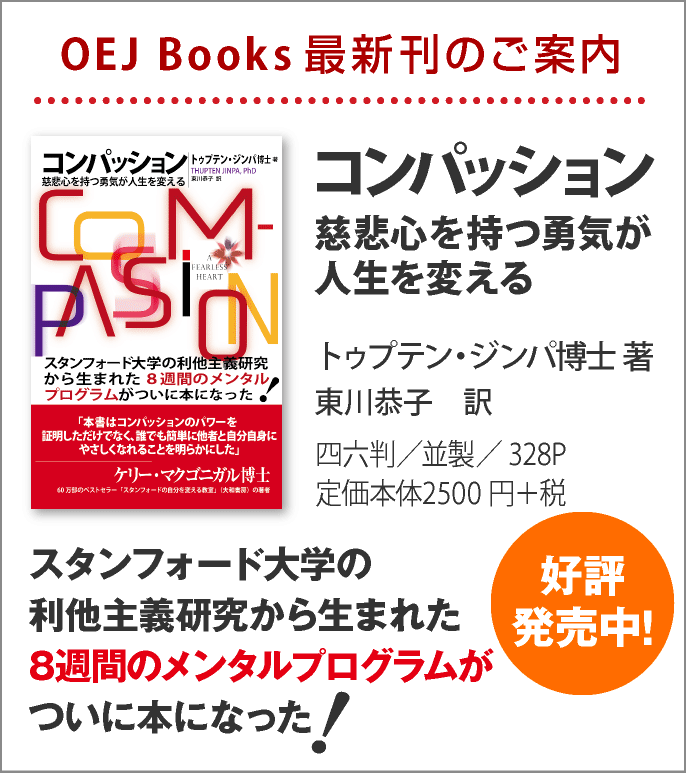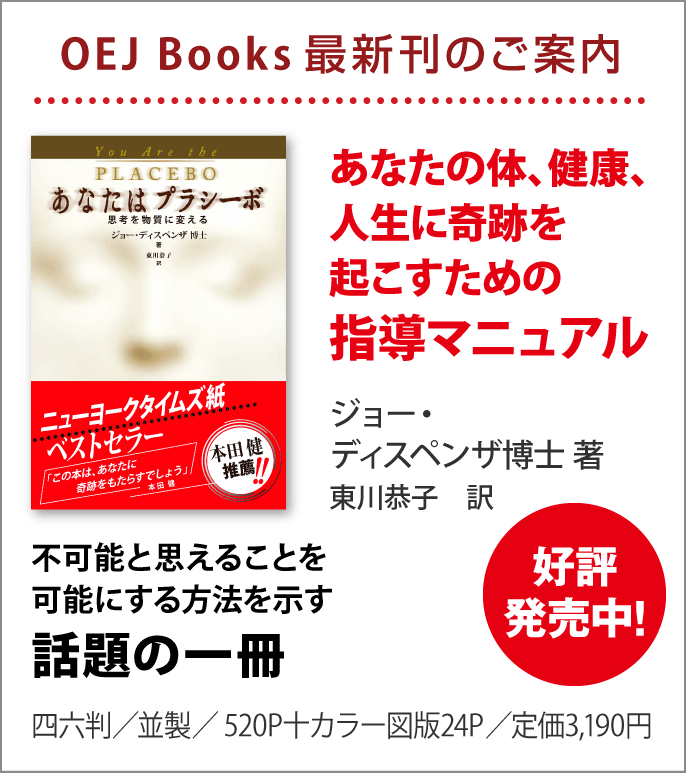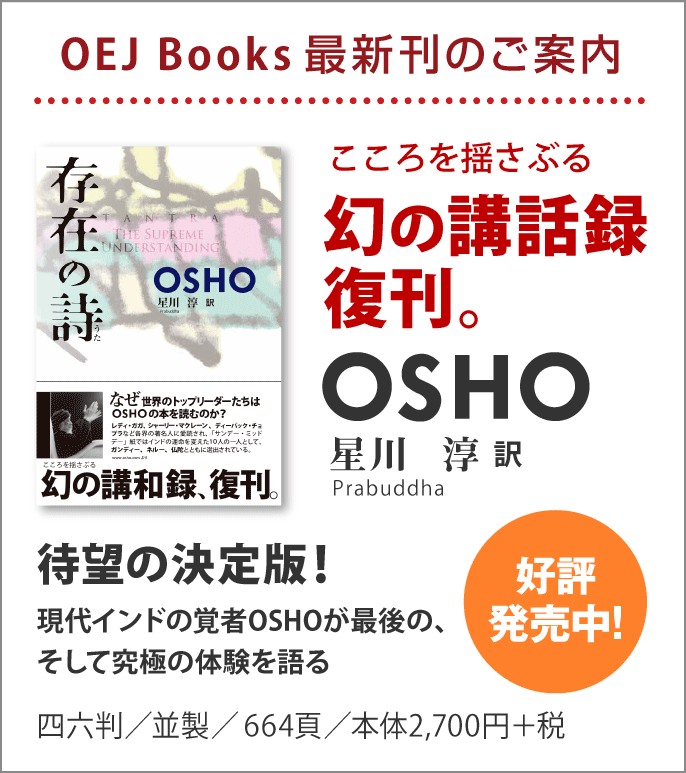私がOSHOの死を知ったのは、OSHOが肉体を離れた日の夜中の12時ころの電話でした。その日、アシュラムにいた友人が電話で知らせてくれたのです。
私たちは、そのころ伊東の小室山にある別荘地に、友人たち数人と住んでいました。OSHOが肉体を離れた日の夕方、そんなに雨が降ったわけでもないのに、私たちの住んでいる家のすぐ目の海が見渡せる丘の山間に、見たこともないような大きな虹が立ち上がったのです。虹といえば普通は遠くに見えるものですが、その日は、まさに手を伸ばせば手が届くぐらいの近さに、しかも、これまで見たこともないほどの大きさで、はっきりとした虹だったのです。その虹を見ながら「チベットかどこかで、誰かマスターが亡くなったんだよ」と、冗談で友人たちとはしゃぎながら話していたのです。というのは、その前年、画家のミラが虹の絵について説明しているときに「チベットでは虹が出たときには、悟ったマスターが亡くなったときだという言い伝えがあるのよ」という話をしてくれていたからです。
しかも、あとで考えると、なんとその虹の出た時間は、まさにOSHOが肉体を離れようとしていた時間でもあったのです。OSHOが最後にブッダホールに現れた日の様子を、私はハワイでビデオで見ました。
OSHOの絵を、ハワイのギャラリーに紹介したらどうかという友人の招待があって、ハワイの友人のところに滞在していたところ、OSHOミステリースクールのディレクターだったカヴィーシャもハワイに滞在していて、彼女が持っていたビデオを友人たちと見る機会があったのです。あとになって見ればわかることなのですが、OSHOはほんとうに立って歩くのがやっとだったことがわかります。
いつものようにブッダホールに姿を表し、彼がいつも講話をしていたブッダホールのポディウムのふちにそって、そこに集った5000人以上の人たちにナマステー(合掌)をしながら、小さく小刻みに足を動かしながら、半円のポディウムの端から、もうひとつの端までゆっくりと小刻みに移動していきます。いつもなら、椅子に座ってみんなとともに瞑想をするのですが、そのまま座ることもなく、ふたたびもと来た入り口へと戻っていきます。これまでカメラの方を見るようなことは一度もなかったのに、最後にカメラの方を一瞥するかのように振り向いて、かすかな微笑みを浮かべて去っていったのです。それは「ブッダホールのかなた、そこにいるすべての人々のかなた、空のかなたを見つめる」まなざしでもあり、そのビデオを見ているものにとっても、ビデオを見ている私たちへの別れの挨拶のようにも思えたのでした。
OSHOが肉体を離れたというアナウンスがあったのは、その3日後のことでした。
シュンニョは書いています。
『OSHOはますます体力を衰えさせ、胃の痛みも増していました。胃のレントゲン写真を撮りましたが、なにも見つかりません。痛みはハラ(丹田)に向かって移動しつつありました。それがハラに達したら命が危ないと、OSHOは言いました。
彼はますます、この世ならぬものとなっていくように見えました。時々、彼は私たちに会うためにブッダホールを訪れました。ブッダホールにいる私は焦燥感から怒りを覚え「行かないで」と立って叫びたくなりました。それでも彼は行こうとしています。私は彼を見るたびに「あなたはひとりだ、あなたはひとりだ」と言われているように思いました。この時期、私はブッダホールのなかでOSHOから離れたところにいたい、うしろの方で踊っていたい、と強く思いました。うしろにいた方が彼の存在を強く感じられ、無をたたえたそのまなざしに悩まされずにすむからでした。ある晩、私はブッダホールのうしろの方で、狂ったように踊りました。夢中になるあまり、あやうくブッダホールを囲う蚊帳を突き破って、外の地面に落ちるところでした。
私は昔のダルシャンでのように泣きじゃくり、無意味な音声を発していました。前の方に座っていると、OSHOが消えつつあるのがあまりにもわかりすぎて、ほんとうにはよろこび祝えませんでした。でも、私がうしろの方に座ったのは、その晩だけのことでした。OSHOが最後にブッダホールを訪れた晩は、彼が入口から入ってきても、まったくよろこび祝う気持ちがわいてきませんでした。私はOSHOの椅子の正面に座っていました。彼は私の方に歩いてきて、見上げる私の正面で足を止めました。それから彼は右を向いて、ポデイウムの上を、ゆっくりと入口から遠いほうへと歩いてゆき、そちら側にいる人たちにナマステを送りました。私はみじめそのものでした。OSHOがポディウムのいちばん端に立っているとき、私は自分に言い聞かせました。
「これがOSHOに会える最後になるでしょう。それなら、みじめさは捨てたほうがいい。そうしないと、死ぬまでそれが心残りになってしまう」
私は音楽にあわせて両腕を動かし、踊りはじめました。OSHOはポディウムの上を、今度は入口の方向へと動いています。彼はふたたび、見上げる私の正面に立っています。彼とのあいだには1メートルほどの距離しかありません。
私たちの目は合いませんでした。
でも、彼がそこに立っているあいだに、私は両腕を振って踊りながら、彼にこのように言ったのです。
「そうなさってください。あなたは私たちのために何年ものあいだ、肉体にとどまろうとなさったのですから。いまがあなたの去るときなら、そのようになさってください」私は腕を振って、彼にさよならを言いました。
「あなたが行かなくてはならないのでしたら、私は、あなたのためにそれがうれしいのです。さようなら。愛するマスター」ポディウムをうしろに下がり、ブッダホールを出る寸前、OSHOは向きを変えて、わずかに右の方に眼を向けて、ブッダホールのかなた、そこにいるすべての人々のかなた、空のかなたを見つめました。
彼の眼にはほえみが浮かびました。
ほほえみとくすくす笑いの中間にあるものでした。
あえて言うとしたら、長い旅をした旅人が、はるかかなたに故郷を認めたときの表情です。
知っているものを認めたときの表情です。
私はいまでも目を開じれば、すぐにそのほほえみが思い浮かぶのですが、それは言葉では言いあらわせません。そのほほえみは、まず彼の両眼に表れ、そして口もとにも表れました。彼がそうして存在に向けてはほえむと、私の顔もほほえみました。
私の知るなかで、もっともあたたかなほほえみ。
私の知るなかでただひとつの真実のほほえみ。
私は顔を輝かせながら、自分がひとりであることを感じていました。OSHOがブッダホールを出るとき、私は両手を頭上にかかげて合掌しました。私は合掌し、彼はいなくなりました。
その晩、私が一緒に食事をとっていた女友だちが、OSHOに会うのは今日が最後だったと思うと言いました。それは私が誰にも言うまいと思っていたことでした。そんなことを口にするのは、あまりにも乱暴だと思っていたのです。
私もそれを感じていましたし知ってもいたのですが、それでもそれを認めたくはなかったのです。私はラフィアを見かけました。「OSHOはどんな具合だろう。ぼくは恐れているんだ」と彼は言います。「私もよ」と言いました。その翌日、私はとても不安でしたが、OSHOが死ぬかもしれないと自分が考えているからだとは認めたくありませんでした。
私はいつも、OSHOが死んだら私も死ぬのだと思っていたのです。
彼のいない人生など想像できませんでした。その夜、私たちには、OSHOは部屋で安静にしているから、私たちは彼なしで瞑想するようにというメッセージが伝えられました。
これは、今になって思いだしたのですが『私がいなくても私の仲間たちが沈黙の深みに達することができるようになったら、そのとき私は肉体を離れよう』と、OSHOが語ったときがありました。
もっとも、その夜の私には、そんなことなどまったく思い浮かびませんでした』
「和尚と過ごしたダイアモンドの日々」
(本書は絶版になっています。 お問い合わせはinfo@oejbooks.comまで)