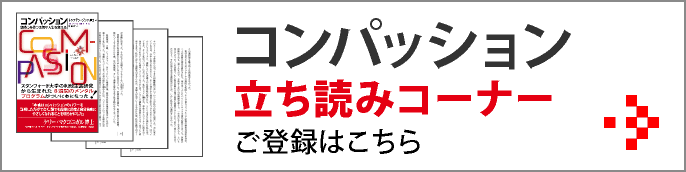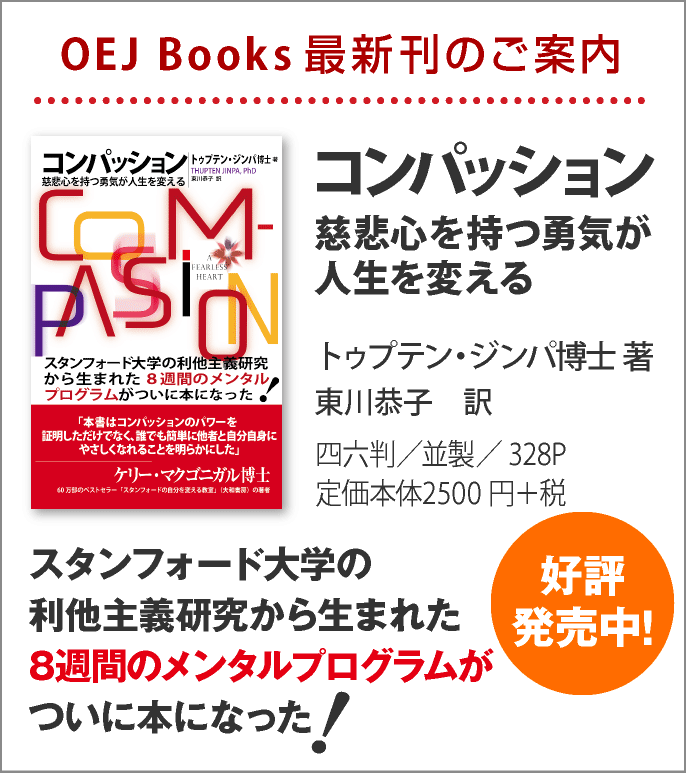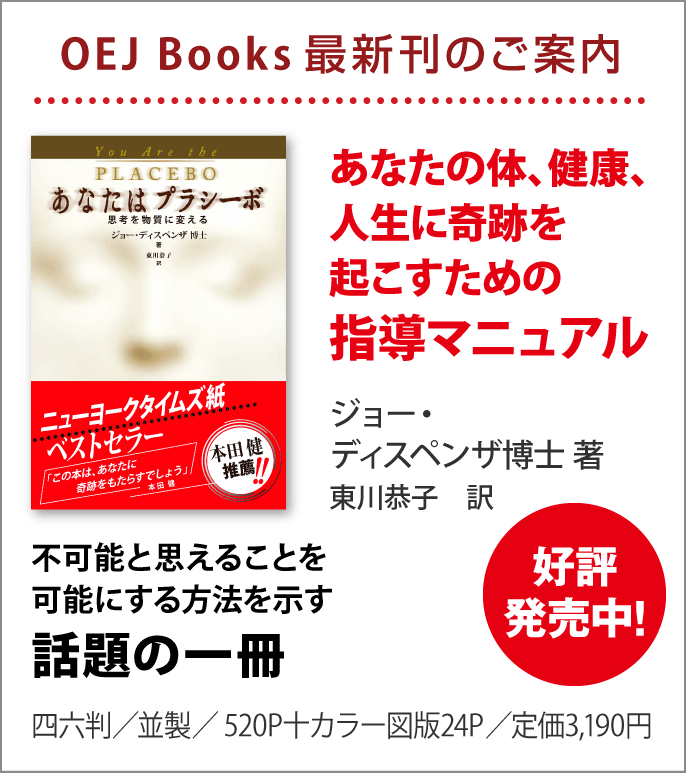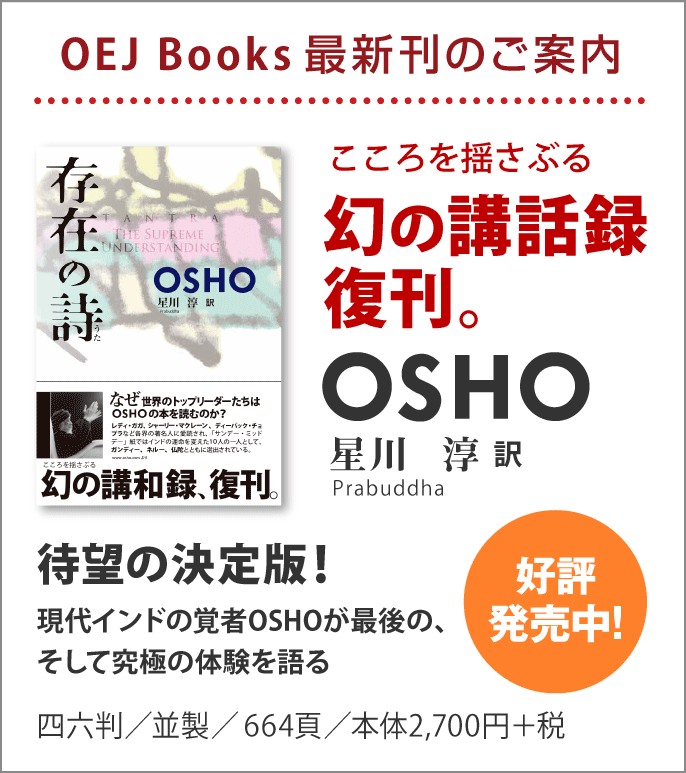何らかの真理を認識するとき
ハートには、
つねにダンスがある
ハートは真理への唯一の証しだ
ハートはことばで
立証することができない
ハートは独自の方法で
立証することができる
ことばではなく
愛を通して
ダンスを通して
音楽を奏でることを通して一ー
ハートは語るが、
ことばや論理によって
語るのではない
「ゴールド•ナゲッツ」 by Osho
真理は哲学や科学によって探求され、見出されるものだと一般には考えられています。
Oshoは、もともとは大学の哲学教授でもありましたので、哲学による真理の探求については知り尽くしています。
そのOshoは語ります。
ハートは真理への唯一の証しだ
これはこれまでの哲学の歴史をこのひと言でぶっ飛ばす、革命的な言葉です。
そもそも、真理とはなんでしょうか?
真理とは、虚偽や誤謬の対義語として、確実な根拠によって本当であると認められたことを意味します。
ですから、真理は論証される必要があり、言語による表現であることが不可欠です。
そこでOshoは語ります。
ハートは語るが、
ことばや論理によって語るのではない
真理は哲学によるのではなく、ハートによって知ることができるのだと。
ちなみに、西欧哲学において真理とは何かについて研究する学問は真理論と言われ、論理学や認識論において問題とされてきています。
哲学の歴史で、これまで何が真理と考えられてきたかを見ると、Oshoの言葉の革新性がわかります。
そういう意味で、以下にこれまでの哲学の歴史の中で、真理についてどのように論じられてきているのかを、少し見てみましょう。
古代ギリシャのプロタゴラスは『真理』と題する書物の中で、「人間は万物の尺度である」と述べました。
そうなると人間には絶対的な共通の認識はないので、真理は相対性であるということになります。
これに対してプラトンは対話篇『国家』において、真理とは永遠かつ普遍的なものでなければならないが、それは実体であるイデアの世界にしかないものであり、この現実の世界は仮象の生成流転する世界であって永遠に存在するものはなにもない、と語ります。
つまり、プラトンは真理は永遠普遍なものと定義して、それはイデアの世界にしかないとしたので、この世は仮象の世界であって真は存在しない、ということになります。
アリストテレスは、真理に到達するためには知識は確実なものでなければならないが、その確実な知識を手に入れるという目的のための「道具」として学問体系を整備して「論理学」を著しました。
この着眼点は現代真理論における記号論理学の発展の基礎となりました。
アリストテレスは、真理とは思惟と実在の一致と定義し、真理論と認識論と存在論がロゴスにおいて一体不可分のものとして語りました。
アウグスティヌスは、プラトンの「この世は仮象の世界であって真は存在しない」という点を修正し、世界はロゴス・真理によって創造されたのであるから、存在するものはすべて真である、と主張しました(真理の存在論的側面)。
新約聖書のヨハネ伝に「初めに言葉がありき。言葉は神と共にありき。言葉は神なりき」とあることから、 人もこの世界の被造物の一つであり、その限りで魂は真理とつながっており、魂は真理を認識することができる(真理の認識論的側面)としています。
そして、魂は「わたし」という意思であり、存在する実体であり、自立している。それゆえに、魂は探求するが、彼を探求に導くものは愛であり、愛は最後の憩いの場として万有の根源である神を求める。
万有の根源である「神は存在である」。神が自己自身を認識することによって、われわれの認識が始まる。神は認識の原理であるとともに真理である。
人は真理を認識するためには、感覚(外的人間)に頼るのではなく、理性(内的人間)によらなければならない。創世記には、神は人間を神の似姿として創ったとあり、神に似るのは動物にはない人間のみが有する理性部分だからである。
理性は外に向かうのではなく、内部に向い、それを超えた至福の果てに真理を見るのである(真理の幸福論的側面)。
アウグスティヌスは懐疑主義者に対し、「わたしも疑う。ゆえにわたしは存在する。わたしは間違える。ゆえにわたしは存在する」として自己の存在は確実であるとした上で、神学者として「宗教的真理」を探究したのです。
トマス・アクィナスは、アリストテレスのロゴスを中心に認識論・存在論と一体化した真理論とキリスト教的神学を統合し、真とは思惟と事物の一致であるとしました。
トマスにとって、神は、万物の根源であり、旧約聖書の『出エジプト記』第3章第14節で、神は「私は在りて在るものである」との啓示をモーセに与えていることを根拠にアリストテレスの存在論に修正を加え、「存在-本質」(esse-essentia)を加えたのです。
トマスによれば、魂は不滅であり、人間は、理性によって永遠普遍の神の存在を認識できる。しかし、有限である人間は無限である神の本質を認識することはできず、理性には限界があり、人間が認識できる真理にも限界がある。
とはいえ、人間は神から「恩寵の光」と「栄光の光」を与えられることによって知性は成長し神を認識できるようになるが、生きている間は恩寵の光のみ与えられるので、人には信仰・愛・希望の導きが必要になる、と考えました。
これによると、人は死して初めて「栄光の光」を得て神の本質を完全に認識するものであり、真の幸福が得られるということになります。
ルネ・デカルトは、数学・幾何学の研究によって得られた概念は疑い得ない明証的なものであり、理性による永遠真理であるとしました。
しかし「我思う 故に我あり」という言葉にあるように、いったんは数学的な永遠真理でさえ疑うという方法的懐疑論を唱えながら、どれだけ疑っても疑いえないものとして純化された精神だけが残ると主張しました。
そこから、彼は、純化された精神に明晰かつ判明に現れるもののみを真理の基準として真理の明証説を提唱し、真理を人間の知性の内部に求める主観主義を唱えました。
ライプニッツは、デカルトが明証という心理的なものを真理の基準としたことに反対し、すべての真理はアプリオリな分析命題であり、分析によって最終的には同一律に還元可能であると主張し、真理の基準を無矛盾性という論理的なものに置きました。
アリストテレス以来の論理学を重視する学問体系が中期プラトンの整合説と結びけたのです。
ヘーゲルは、永遠で変化しない真理という概念をひっくり返し、真理は弁証法によって発展するものであって、矛盾は真理の対立概念ではなく、かえって真理の発展原因なのであり、その発展運動の整合的全体こそが真理なのであるとしました。
ヘーゲルの整合説は、デカルトと同じく認識論を出発点としながらも存在論を含めたのです。
ヘーゲルに対する厳しい批判者であったニーチェはさらにもう一度真理という概念をひっくり返しました。
ニーチェはカントの「主観/客観の二項対立図式を前提としつつ、現象と物自体を厳密に区別する」考え方と、ショーペンハウアーの「理性によっては認識できない物自体という概念を維持しつつ、現象とは私の表象であり、物自体とはただ生きんとする盲目的な意思そのものにほかならないとして理性を批判した」考え方を引き継ぎ、「生とは、すべてを我がものとし、支配し、超え出て、より強くならんとする権力への意志である」とし、従来の真理の概念をひっくり返し、真理は一種の誤謬であるとしました。
ただし、それはそれなしではある種の生物である人間が生きてはいけないという厳しい条件のついた誤謬であるとして、真理を理性と共に生に従属させ、人の生に有用であるか否かをもって真理の基準と考えました。
ウィリアム・ジェームズはその主著『プラグマティズム』において、思想の意味を理解するためにはその思想がもたらす行動こそが全てであるとし、思想を自然を改変するための道具と位置づけ、思想が生存するために必要な実利に合致するならばそれは真理であり、真理の役割とは現実に思考を方向付ける過程にあるとしました。
他方で、彼は、厳しい自然の中で人間の生存に不可欠なものとして慣習的に発展してきた常識を重視し、性急な改革を戒める。真理とは長い時間をかけて常識によって発展してきた信用制度によって確立されており、信念や思想が反発されない限りはそれは真理として妥当するのであると考えました。
フッサールは、現象学を提唱し、真理とは志向的対象が自体所持において根源的に与えられていることであるとしました。
つまり、アリストテレス以来多くの者が思惟と実在の一致、認識と存在の一致などデカルト的な主観/客観の二項対立図式を前提に対応説をとってきましたが、現象学においてはかかる図式自体が放棄され、真理は現象学的還元によって与えられるものと考えたのです。
フッサールの弟子のマルティン・ハイデッガーは現象学を方法論として存在論に応用することで新たな真理論を打ち立てました。
ハイデッガーは、ニーチェを形而上学の完成者であるとしてその真理論を批判し、プラトンに始まり現在に至るまで存在者のみに目を奪われ、存在を忘却する存在忘却の歴史に陥っているとしました。
彼は、『存在と時間』において、真理の語源ギリシア語のアレーテイアーに遡って考察し、真理とは隠されたものを戦い奪う、つまり「隠れなさ」という意味であると定義しました。
ついで、現象学的解釈学・基礎的存在論を展開し、人間は現存在であると同時に世界内存在であって、そもそも主観と客観の区別はなく、環世界に存在している。頽落して世間に埋没して存在する非本来的な現存在は、世間や自己の見方に執着しているので、内世界において出遭う存在者は非本来的な隠れたあり方をしている。したがって、生は、ニーチェが述べるように人間が認識しえるものではないが、真理は生に従属するだけのものではない、と考えました。
そして、本来的な現存在が自身をこの執着から解放すれば、存在者が全体として自らを本来のあり方そのままで現れる、これが真理であり、その本質は自由である、としたのです。
さらに、彼は『ヒューマニズムについて』において、言葉こそ存在の家であり、言葉のうちにこそ真理は宿り、存在の明るみが性起する限りにおいて存在を己を人間に開示する。あらゆる知の根拠である存在の開示は、生の生成過程における生の自己差異化、二重性の表れであり、現存在が脱自的に存在者に身をさらしているときに真理は体験され、感じられるのであり、驚き、感動、落涙などを伴うのである、としたのです。 (以上、ウィキペディア他 よりのまとめ)
このように、哲学は真理を探究してきているのですが、それらはすべて言葉、ロゴスに基づいています。
Oshoは、真理はこのような哲学や言葉によって得られることはないと語っているのです。
つまり、これらの哲学のすべてをぶっ飛ばしたのが、この洞察です。
何らかの真理を認識するとき
ハートには、
つねにダンスがある
ハートは真理への唯一の証しだ
ハートはことばで立証することができない
ハートは独自の方法で立証することができる
ことばではなく愛を通して
ダンスを通して
音楽を奏でることを通して一ー
ハートは語るが、
ことばや論理によって語るのではない
これは、Oshoが悟りを得て、自らが真理を得たことの体験から語っていることです。
これまでの哲学者で悟りを得た人物を知りません。
仏陀の言葉は真理の言葉と言われていますが、それは悟りを得たものによる言葉だからです。
それは論理や言葉を超えた真理であり、哲学によって知ることはできず、マインドによって知ることはできず、ハートによって知ることができるものだ、というのがOshoの真理への洞察です。
今日はここまでにします。
えたに