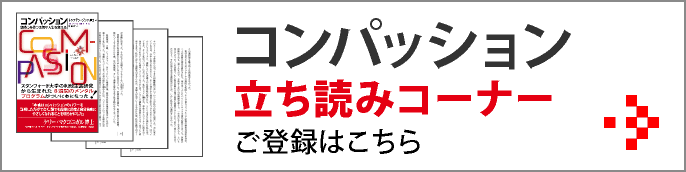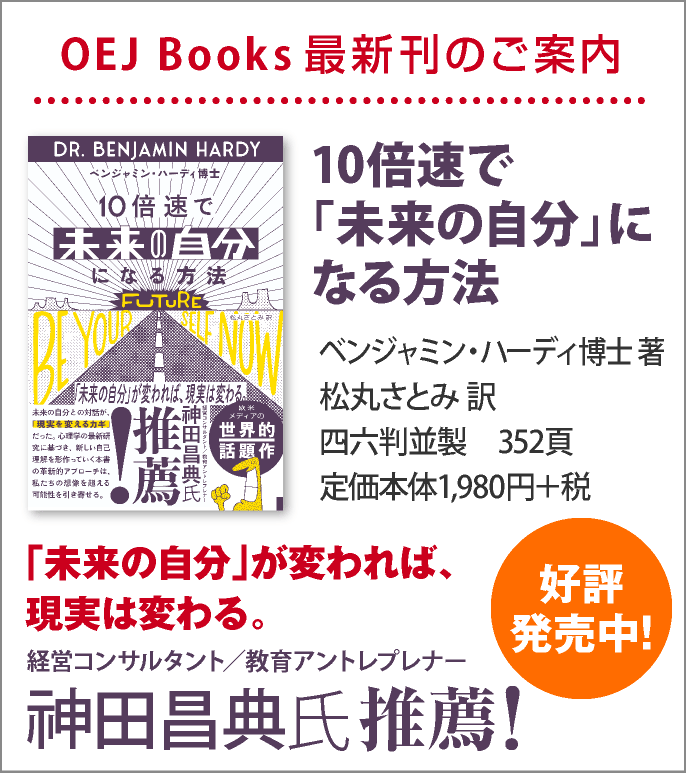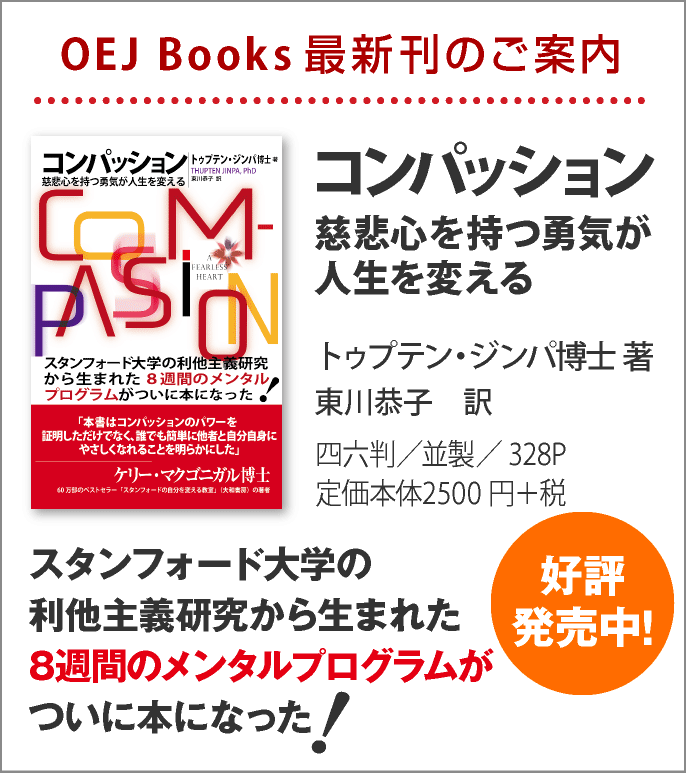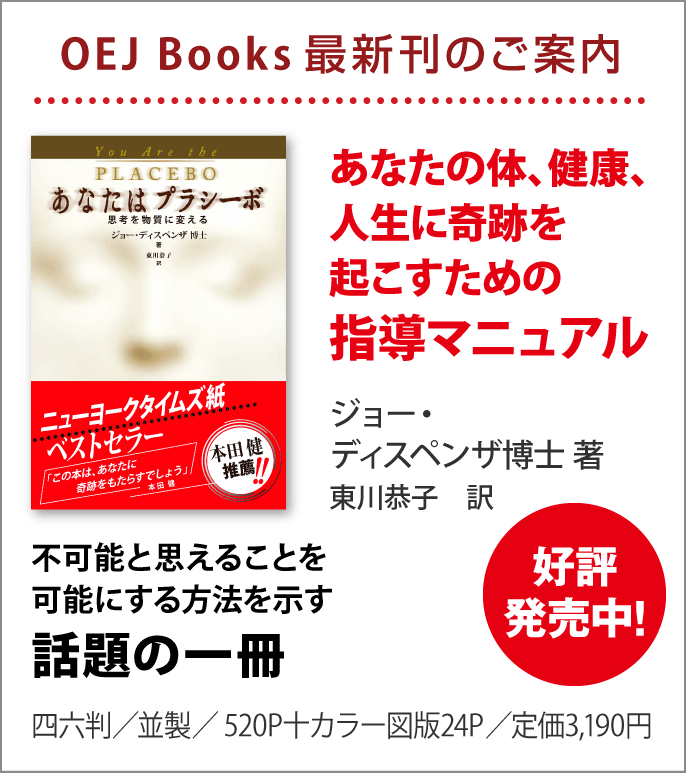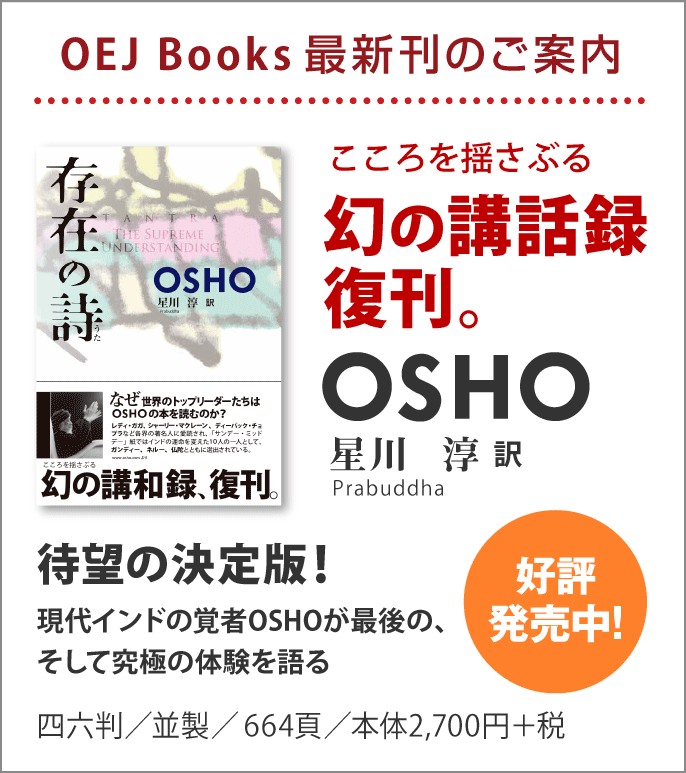どうしてOSHOは死についてこれほどまでに確信に満ちて語ることができるのか、理解しかねるところがあります。
普通,死とは体験できないものなので、誰も死については語ることができないはずです。語ることができるとすれば、せいぜい臨死体験までですが、たとえ臨死体験をしたとは言っても、結局は生き返っているわけなので、ほんとうに死んだと言えるかどうかは疑問が残ります。ところがOSHOはその死について『死は肉体に起きるのであって、あなたの存在に起きているのではない』と語ります。その死の実相について、OSHOの「死について 41の答え」という本に詳細に述べられています。
この本はOSHOの650冊以上にわたる全著作から、いかに生き、いかに死ぬかのエッセンスを抽出したものですが、『これは私の体験からのものであり、あなたへ挑戦状だ』とも述べられています。
つまり、死について、OSHOは体験として知ったことであり、それはあなたも知ることができるものであるのだから、それが本当かどうかはあなたが自分で知るようにしなさいということなのです。そして死を体験するための瞑想法もその本のなかでに書かれています。
OSHOの秘書を長年務めていたマニーシャは、ターミナルケアなどをしながらそのOSHOのヴィジョンを多くの人々と分かち合っています。
そのマニーシャがOSHOの生と死についてのヴィジョンを分かち合うワークショップを開催します。※こちらは終了しています。
「OSHOバルド」では、死のプロセスについての体験をするヒントにもなるでしょう。
ションニョからの質問に答えて、OSHOは語ります。
(「セックスと死」その4)
あなたが、みじめさと苦しみのなか、無意識に生を送ってきたなら、あなたは死が訪れる前に昏睡状態におちいるだろう。そうなってしまったら、オーガズムは感じられない。死はあなたに起きているのではない、あなたの存在に起きているのではない、そうではなしに、それはあなたの肉体に、つまりあなたが使ってきた乗り物に起きているにすぎない、という気づきも得られない。この質問をしたのが男性だった場合にも、同じことが理解されるべきだ。だが、男性が死を想起するまでの高まりに達することはまれにしかない。
男性のエネルギーはとてもダイナミック、とても活動的なために、そうした高まりに達する前に放出されてしまう。だから私が思うには、これは女性からの質問だ。そしてこれまで、だれも女性の言うことには耳を傾けなかった。女性がなにをどのように感じているか、だれも気にかけてこなかった。これは幾世紀もの昔から男性が思ってきたことで、インドにはこの現象をあらわす絵画や彫刻があるのだが、男性は女性のなかには死のようなものがあると感じる。それは誤解だ。それは女性のなかにあるのではなく、あなたの性エネルギーそのもののなかにあ るのだから。だがこれは、男性があれこれのことを他人に投影するお決まりのやりかただ。彼ら自身の性エネ ルギーが死を身近に感じさせるのだが、彼らにはそれが理解できない。男性の性エネルギーは死を想わせるほどの高みには達しないので、それをはっきりと理解できないのだ。
一方女性には、耳を傾ける人さえいたら、この現象について多くを語れるだけの知恵がある。知恵ある女性はキリスト教に滅ぼされた。中世には何千人もの女性が焼かれた。『魔女』というは、知恵ある女性を指す言葉にすぎなかった。それなのに、彼女たちはあまりに糾弾されてきたので、 言葉そのものまで非難の響きを帯びるようになってしまった。そうでなかったら、 これは敬意のこもった言葉だ。賢者と呼ぶのと同様だ。知恵ある女性たちは世界じゅうにいた。知恵ある女性だけが 洞察を与えられる問題というのがあったのだ。
インドの彫刻と絵画には、あなたがこの現象を理解しないかぎりとても奇妙に思えるものがある。たとえば、横たわるシヴァの胸の上で、妻のシヴァニが踊っている。片手には抜き身の刀、もう片方には切り落としたばかりの首だ。彼女は生首を連ねたネックレスをしていて、生首のひとつひとつか ら血がしたたっている。彼女は狂ったように踊っている。彼女はシヴァを殺してしまいそうに見える。その踊りはあまりにも狂っている。女性がこれほど狂ってしまったら、シヴァにはもう勝ち目が ない。私が話してきたことはこうした体験と関係がある。東洋は女性に耳を傾けてきた。西洋で起きたようなこと――女性を殺したり焼いたりすること――は東洋では一度も起きなかった。
知恵ある女性の 言うことはつねに聞かれ、女性の知恵は吸収されてきた。女性は人間の半分だからだ。男性の知恵は半分だ。女性の知恵を吸収しないかぎり、男性の知恵が完全なものになることはない。女性の側からの体験はどのようなものなのか、女性に尋ねる必要がある。
「和尚と過ごしたダイアモンドの日々」
(本書は絶版になっています。 お問い合わせはinfo@oejbooks.comまで)